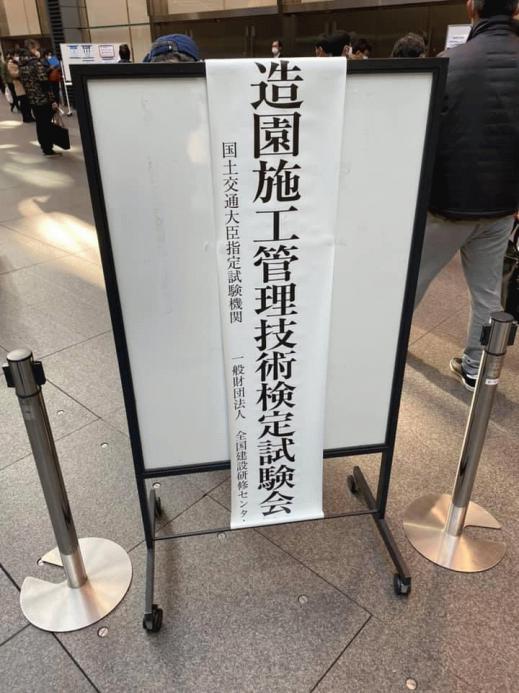2020/12/07
「1級造園施工管理技術検定試験を受験いたしました」(週刊生コン 2020/12/07)

透水性コンクリート(他、環境コンクリート)はあらゆる分野を横断する知識が求められる。生コン、硬化コンクリート、舗装、土木、建築、そして造園。自然と人が調和する世界を創造するコンクリートテック普及の道。「1級造園施工管理技術検定試験を受験いたしました」(週刊生コン 2020/12/07)。
2020年コロナ禍の試験会場
東京国際フォーラムが試験会場。
通常資格試験といえばその辺の大学の教室で行われる。
ただ、今年はコロナ禍ということもあり、感染症対策バッチリで例年とは様相が違う。
外みたいなところで受験したのは初めてだ。
しかも、隣の人との距離がしっかり確保されていて、これじゃカンニングできねえじゃん笑、という環境だった。
さらに、会場が開放されたのも説明開始直前。
僕は結構ギリギリで会場に到着したため難なく過ごしたが、他の受験生の方々はおそらく例年通りずいぶん前から会場に到着していたのだろう。
いい大人たちがひと頃の高校生のように地べたに座ってテキストを開いていた笑。
ひと頃の高校生も電車の中で地べたに座ってテキスト開いてたら微笑ましい光景だったろうに。
数百人といる受験生の中で僕だけブログ用の写真撮影していた。
まあまあ浮いていた。
例年にないこの空気を楽しめるほどの余裕はなかったが、それでも解答用紙を埋めるときの手は去年ほど震えてはいなかった。
https://www.jctc.jp/exam/zouen-1
問題1:経験記述
(1)工事名:
正蓮寺境内ロータリー新設他工事
(2)工事の内容
①施工場所:
静岡県伊豆の国市南江間地内
②(ア)この工事の契約上の発注者名または注文者名
注文者名:
正蓮寺こども園
(イ)この工事におけるあなたの所属する会社等の契約上の立場を、回答欄の「」内の該当するものに⚪︎
③工期:
2020年7月1日〜2020年9月30日
④工事金額または請負代金額:
11,800,000円
⑤工事概要
(ア)工事内容について具体的に記述
降雨時裏山から雨水が境内に流入し排水が問題となっていた。また、シダレザクラやウメなど植栽の根に雨水の浸透・供給の保全。区分された隣接幼稚園・保育園と境内の敷地を統合することによる土地の有効利用。新設するロータリーのイベント他の利用など、各施設を統合した敷地として利用するための改修工事であった。
(イ)工事数量について具体的に記述
地盤工:地下暗渠設置 20m
砕石路盤工 543.8m2
園路工:透水性コンクリート舗装工 543.8m2
擁壁工:ブロック積み擁壁工 H1.8 L15m
放送設備工:スピーカー16基
照明設備工:照明 15基
樹木手入れ:シダレザクラ 樹高H=10m 目通り周=0.21m 1本
ウメ 樹高3.0m 芝付け周=1.0m 1本
(ウ)現場の状況及び周辺の状況について具体的に記述
工事箇所は幼稚園、保育園、寺院が入り組んで建築された敷地の一部(境内)であり、大型機械の搬入はできず、各施設の運営の都合上工事に対する制約条件も多く、大掛かりな工法を選択できないため、人力中心の施工となった。
(3)工事現場における施工管理上のあなたの立場
工事主任
(4)上記工事の施工において、課題があった管理項目名(工程管理または品質管理)及びその課題の内容(背景及び理由を含む)を具体的に記述
①施工管理項目:品質管理
②①で選んだ施工管理項目上の課題の内容を具体的に記術
本工事は隣接する保育園、幼稚園、と一体となった敷地として境内に、各施設共用のロータリー、排水設備、放送設備、照明設備を新設する工事であった。
裏山からの流水の排水と、植栽の根への雨水の浸透・供給の両立を図るため、環境負荷が小さく、耐久性の高い透水性コンクリート舗装が採用された。工法上推奨されているアスファルトフィニッシャによる連続施工ができず、人力施工となったため、施工の品質と出来型の管理が課題となった。
(5)(4)の課題に対し、あなたが現場で実施した処置また対策を具体的に記述
①機械施工の精度を再現するため、ロータリー幅員の両脇に設置された型枠の高さをよもりも含んだ高さ(設計厚100mm、よもり20%、敷設120mm)とし、幅員の長さ以上の定規を利用して均すことで、平坦性を確保した。
②材料を適切な状態で締め固める(プレートコンパクタによる転圧)ことで、骨材剥離や空隙つぶれを防ぐために、材料のコンシステンシーを専門に管理する人員を配置し、そのものに作業員に対する適切な転圧のタイミングを指示させた。
③連続施工が中断することで施工ジョイントが品質・出来型の問題とならないよう、あらかじめ定められた延長ごとに角材で一旦完成させ、その箇所を収縮目地として次のスパンの施工を行った。
2020年1級造園施工管理技士試験を終えて。
市販のテキストは6回以上繰り返して学習した。
(自分のペースが乱されるのが苦手なので独学が例年の慣いとなっている)。
経験記述も、昨年のように嘘偽りを書いていない、実際にあった現場をベースに記述した笑。
(多分、昨年はテキストの例文の内容をマイナーチェンジして解答したのが敗因)。
やるべきことは、やり切った状態で試験に臨んだ。
でも、試験開始後問題用紙をざっと眺めて感じたこと。
「造園の神様に造園な面なって言われてる気がする」
テキストには出てこない内容から問題が始まっていた。
これ、資格試験あるある。
最初に受験生の出鼻を挫く作戦。
わかってはいても、手が震える。
1年近く勉強してきたのに、その学習が無駄になる恐怖。
そこに打ち勝って解答を進めなければならない。
まさに心理戦だ。
難問は無視して、次の問題にすぐに切り替える。
問題2はそんな感じで進めていたら、ほとんどが空欄になってしまっていた。
心が多少折れているため、問題が冷静に飲み込めないのもあったが、さらに心が折れる。
それでも切り替えて、選択問題4に移る。
選択問題4は概ねテキストが網羅している範囲からの出題であったためおよそ9割は解答欄を埋めることができた。
7割が及第ラインと言われているため、問題4はクリアしただろう。
さて、それこそ問題の問題2に戻る。
「ぶりがつく」というのはまさにこういうことなのだろう。
先ほどまでほとんど埋めることができなかった解答欄だったが、今度は冷静に問題を咀嚼することができ、先ほどほどの悲惨な状態ではなかった。
確信は持てないものの、それなりに空欄を埋めることができた。
土壌中の排水層の施工など、出題方法がテキストのそれと違っていたため、思い当たるのに時間がかかった。
道路使用許可証などもテキストでは網羅していない内容だったから自信を持って解答が作れなかった。
今、インターネットで確認したところによると、おそらく正解のようだ。
問題2は安全側(失敗が多かったと仮定)で見ておそらく、5〜6割の正答率だったように思う。
造園の神様に造園なめんなって言われてる気がする。
今年の4月頃、6月末に予定されていた舗装施工管理技士試験の勉強をしていた時にふと気付いた。
願書申し込み受付期間 令和2年2月14日(金)〜2月28日(金) 締切日の消印有効
ギャフン。
過ぎてる。
茫然自失としていた。
何せ、昨年12月1日造園施工管理技士の試験終了直後から学習を始めていたのだ。
半年近く勉強していたのだ。
願書受付期間が終わってるっ。
(運がいいことに?コロナ禍で試験は中止となったようだ)。
そこからの、一念発起、造園施工管理技士の学習が始まった。
草花の名前や、樹木の種類、品質規格基準(樹姿、樹勢)などの学習。
5月からスタートしたとしても、7ヶ月は造園に没頭していた。
おかげで、草花の名前もずいぶん覚えた。
趣味のランニング中に眺める樹木もなんであるか、どのような性質であるかもわかるようになった。
知識が入ってきたことにより、見える世界の景色が変わったという経験ができた。
生態系についてずいぶん興味を持つようになった。
ある程度の期間がたった今だからこそ、自然と人が調和する世界を具現化するコンクリートテックの普及の役に立つ習慣ができたと心から言える。
知識に深みが増した。
本当に学習してよかった。
それでも、不合格の時は、不合格になる。
それが、資格試験だ。
「合格が目標じゃないし、ずいぶん知識も増えたから、これでいいや。諦めよう」
とはならない。
来年3月に発表される結果が仮に不合格だったとしたら、来年もその日から学習を始めよう。
今度は選択問題から受験し直さなければならない。
そのことでさらに知識は本物となるはずだ。
前向きに考えよう。
資格試験の本来の目的は合格証を手に入れることじゃない。
額に入れて壁に貼っておくもんじゃない。
知識を得て、仕事に活かし、世の中の役に立つことだ。
それでも、やっぱり、受験て緊張するし、疲れるよね。
でも、負けない。
「(コンクリート)主任技士持ってる奴らなんかより、俺の方が現場を知ってる。資格だけなんかいらない」
そう豪語して周囲を白けさせ、そのことを社長に叱られたら不貞腐れて、それまでみくびってた近くの生コン工場に転職したキャバクラ狂いの豚技術者もいた。
「ポンプ業界初の飛び級主任技士合格!」を宣言して、途中で難しいのがわかったのか、「会場に行ってみてびっくり。事務員さんが間違えて技士試験申し込んじゃった」とSNSではかっこいいことばかり書き散らかして敵前逃亡する田舎者ポンプ屋もいた。
(資格試験の話題には必ず登場するお二人さんにはギャラを払うべきだろうか笑)。
僕は、どんな結果でもしっかりと受け入れる。
負けは、負け。
今年もコンクリート技士、主任技士試験を大勢の方が受けられただろう。
勝って笑う人もいれば、努力も虚しく負けて涙する人もいるだろう。
上記の偽物の人生を歩んでは欲しくない。
負けたら、次に勝てばいい。
人生いい時ばかりじゃない。
でも、負けて悔しい思いをしたり、挫折したりしているのは、それは闘っている証拠。
前に進んでいる証拠。
歩みを止めれば、傷つくこともなければ涙することもない。
だから、闘い続けたい。
すると、ある時ある瞬間に気づくのだ。
自分の実力が見違えるように変化していて、以前は問題だったことが今では問題ですらなく、成長している自分の姿に気づく。
世界の景色が見違えて見える。
共にそんな成長を果たそう。
負けるな。
「1級造園施工管理技術検定試験を受験いたしました」
資格試験への挑戦に終わりはない。
宮本充也