2018/09/25
「北海道はどうして極端に土間コンが少ないのか? pt3」
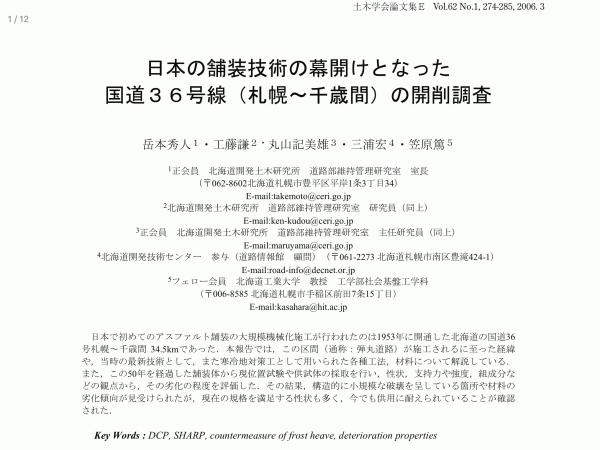
初期凍害や凍上など寒冷地特有の施工条件はたしかに土間コンクリートにとって不利ではあるが、それ以外にもあるはずの「北海道はどうして極端に土間コンが少ないのか?」に迫るシリーズ最終稿。その理由はまだほかにもあった!
日本の舗装技術の幕開けとなった国道36号
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsceje/62/1/62_1_274/_article/-char/ja
僕自身興味を持ってあれこれ調べている時に見つけた論文。
現在、日本の舗装におけるアスファルトとコンクリートの割合は、
95:5
とコンクリートはアスファルトに大きく水を開けられている。
これが普通だと思っていたが、
なんとこの論文によれば1950年以前の舗装の標準は、
コンクリート舗装
だったとされている。
(日本で最初の生コンクリートプラントの創業は1945年11月18日)
あまりの意外な展開に驚いている。
舗装の生態系の覇権はもともとコンクリートにあったものの、
なんと1952年以降のアスファルト関係者の努力の賜物で、
その覇権をむざむざと生コン産業は譲ることになっていた。
そんな歴史があったとはまったく知らなかった。
そして、その幕開けの土地が国道36号(北海道)だったことは、
北海道地区で舗装の標準の地位を確実なものとしたことは容易に想像ができる。
日本全土95%の舗装がアスファルトである現在の原点はつまり北海道にあったのだ。
北海道でコンクリート舗装を採用することはつまり、ブラジルで野球をするようなもんなのだろう。
北海道はアスファルトの地域です!
と言っても過言ではないということだ。
そして、もう一つの理由。
ここにGoogleから引用した北海道と静岡県の興味深いデータを紹介する。
・北海道の面積:83,450km2
・北海道の生コンクリート:255件
※生コン1件あたりのカバー面積327km2/件
・静岡県の面積:7,777km2
・静岡県の生コンクリート:135件
※生コン1件あたりのカバー面積58km2/件
僕が散々問題提起している1時間30分の壁がJISでは設けられている。
つまり、生コン工場の運べる範囲は限られている。
その前提条件の中で実に静岡県の6倍以上もの面積を供給範囲としなければならない北海道における生コンの負荷は相当なはずだ。
アスファルト発祥の地域という元々のアスファルト優位に加えて、
JISの1時間30分という制約は生コン舗装の活躍のフィールドを制限してきたはずだ。
だからってこのままでいいのか生コン舗装?
たしかに選ばれない理由は嫌という程あった。
(※これ以外にも僕が見つけることのできなかった理由はあるはずだが)
だからってこのままでいいのか生コン?
人口低迷は続く。
経済成長の申し子、生コン産業の活躍のフィールドはますます狭まっていくだろう。
その中で唯一広がる市場として目を向けることができる場所。
舗装
という市場。
そこをアスファルトにこのまま永遠に水を開けられていていいのか?
今、北海道地区でも透水性コンクリート「ドライテック 」が普及し始めようとしている。
土間コンが採用されづらい理由ごとに透水性コンクリートのメリットを説明する。
・凍上;地盤が動くことに対処するためには版厚を確保することが有効。通常100mmを標準としているが、150mm(コスト増)にすることで割れなどを防止できる
・初期凍害;透水性コンクリートの最大の特徴「ブリーディングがない」ことで仕上げまで30分で済ませることができる。迅速施工は初期凍害を防止する上で非常に有効
・JIS1時間30分の壁;透水性コンクリートはJIS規格製品とはなっていない。そのため、JISという鎖を気にすることなく自由な普及活動を展開できる
だからって、骨の髄までアスファルト文化が染み込んでしまっている寒冷地北海道での透水性コンクリート舗装の普及はきっと困難を極めるだろう。
ほんの一握りの同志達と。
この北海道という土地に透水性コンクリートという土間コンの常識を広げていく。
そんな試みが始まっている。
「どうして北海道には極端に土間コンが少ないのか?」
いくつかの理由がわかったのであれば、
闘い方は自ずと見えてくる。
極北の土地でも凍結しづらく耐久性に秀でた透水性コンクリート舗装が普及する日がやがて訪れることだろう。
当事者が諦めたら全ては終わりだ。
宮本充也










