2016/08/05
「奇跡が起き始めている」生コン屋のIT戦略
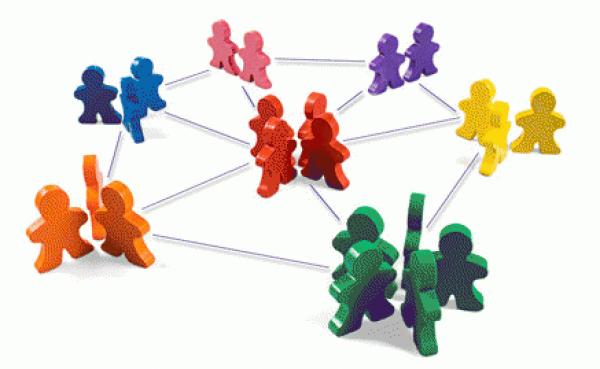
住んでいる場所が同じ
コミュニケーションが生まれやすい。
近所づきあいというのはせいぜいどうだろう、
半径1㎞くらいの範囲ならご近所さんとして認識される。
住んでいる、
・地域が同じ
・県が同じ
・国が同じ
・卒業した学校が同じ
・・・etc
ということにアイデンティティを見出し互いに安心感を得る心理がある。
同じ地域に住んでいる人には融通を聞かせたい、そんなのもある。
ただし、都市生活者なんかには、
・隣に住んでいる人と顔合わせたことない
なんてのはざらで、1000万人もの人口が限られた狭いエリアに住んでいるのだから、
・地域が同じだから信頼します融通できます
なんてことがありえなくなった時代でもある。
上記は、情報が、
「物理的に近いところに伝わりやすい」
という性質をとらえているものだと思う。
ただし、IT革命以降は、この「近いところ」という点が希薄になった。
お隣さん同士
という物理的な近さと情報の流通量(コミュニケーション量)は相関関係を失う
そんなことを実感することが2度も起きた。
1つは、富山県の松嶋建設https://www.e-matusima.co.jp/outline.htmlさんは、
とある工事案件でとても悩んでいた。
日ごろ相談しているパートナーに相談してみてもなかなか解決策が見当たらない。
IT以前は相談できる範囲が、「ご近所さん」のパートナー。
解決策はその範囲で保有されている情報がすべてとなる。
また、ご近所さんは「選べない」のも事実。
たまたま、
・生まれた土地
・勤めている会社の所在地
という地域をベースとした交流になるから、外的要因に支配されやすい。
松嶋建設の松嶋さんは、静岡県に住んでいる生コン屋の僕に相談をした。
※生コン技術にかかわることが大半だったため
僕なりに思い出した人たち、
・福井県の圧送業者
・広島県のモルタル製造者
・全国の土木会社(YDN)
・全国の生コン工場(GNN)
がグループになっているチャットに松嶋さんに代わって相談を投げかけてみた。
たった5分もしないうちに
同じく富山県のあづまコンクリートhttps://aduma-con.com/の毛利さんが、
問題解決の提供をするために、松嶋さんに会う約束を取り付けた。
こんなことが実際に起きる時代になった。
同じ市町に住んでいても、情報伝達がないばかりに、
必要と可能
が結び合うことがこれまでなかったことが実にわかる。
これまでは「物理的に近い」という要因が情報を支配していたが、
これからは「志向が近い」に支配要因が変化していくんだと思う。
物理的に近い<志向が近い
になっていき、物理的な近さは、志向が近いを補う機能になりつつあるんだと思う。
そんなことを感じたのは、
石川県に住む一般の方が当社WEBサイトを閲覧され、
透水性コンクリートドライテックに興味を持たれた(志向が近い)。
興味の赴くままによくよく調べてみると、
ご自身が住む地域にある生コン工場の金沢生コンがドライテックをやっていることを知った。
静岡の会社よりも地元の会社のほうが親近感もあるし連絡しやすいのでTEL(物理的に近い)
つまり、
石川県→静岡県→石川県
という情報の流れと、実際に工事を検討にはいった場合、
石川県→石川県
という物の流れが発生することになる。
住んでいる場所(物理的な遠近)
に支配されていた時代はつまり自分以外の外的要因がウェイトを占めていたが、
上記に見られるように、IT以降は、
志向の遠近
という主体的な内的要因「自らはどうする、どうしたい」がウェイトを占めるようになる。
その意味では、「××だから仕方ない」「○○さえあってくれたら」
から、「××するようにする」「○○が好きだ」という主体的言語が中心を占めるようになる。
自らの内面から湧き上がる志向に素直に生きることができる時代になったということ。
生コン屋のIT戦略を標榜し丸5か月が経過し、上記のような成果が多く表れてきた。
未だに大志なき商材あさりのやからも後を絶たないが、
適切な情報発信が本当に困っている人のところに届いて、
その困ったを解決できる人とつながりを創ることができるのもIT戦略。
物理的な遠近→志向の遠近の時代、
人間が本当に人間らしく外的要因に左右されることなく暮らしていける時代になったんだと思う。
まさか、僕が生きているうちにこんなことが建設産業で起きようものとは、
16年前には想像を全くしていなかったけどね。
宮本充也










