2021/02/01
《奴隷制度と舗装の常識》「コンクリート舗装における炭素吸収の解明」解説(MIT)
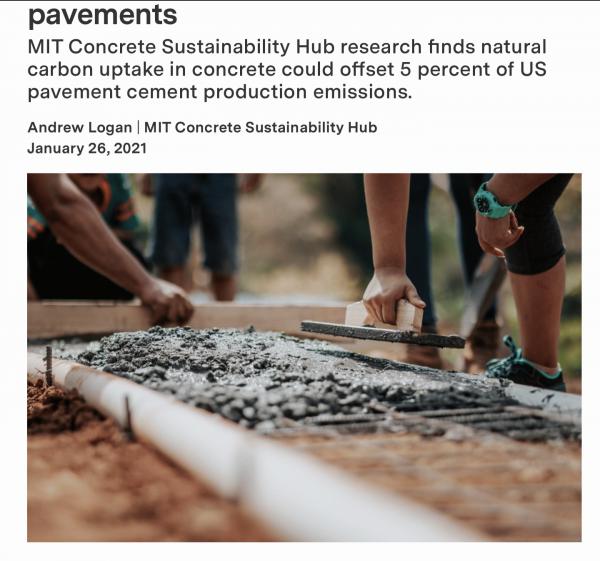
CCU、カーボンニュートラルとポーラスコンクリート(透水性コンクリート)舗装、残コンに関する考察と発信を繰り返す日々に野口先生からMITの記事共有があった。Unravelling carbon uptake in concrete pavements. カーボンニュートラルの鍵はコンクリート舗装にある理由が解き明かされる。
コンクリート舗装の中性化は、米国の舗装セメント生産排出量の5%を相殺
(出典:https://news.mit.edu/2021/unravelling-carbon-uptake-concrete-pavements-0126)
⚫︎参考記事1: 《コラム》「透水性コンクリートの本当の価値は水を透すことではないのかも知れない」
⚫︎参考記事2: 「再生砕石がCO2を固定化することが分かっているのなら、残コン再生コンクリートの中性化度合いはより大きいのではないか」
⚫︎参考記事3: 「ポーラスコンクリートが残コンと出会う時」共同研究
⚫︎参考記事4: 「大地を削らない、汚さない、蓋しない、CO2を収容するコンクリート」blue planet・ポーラスコンクリート
⚫︎参考記事5: 「三菱商事、CarbonCureらとの共同実験に参加する生コン製造者を募集しています」CCUコンクリートの実装
コンクリート舗装の表面対体積比
毎日毎日CCU、カーボンニュートラル、ポーラスコンクリート、残コン、プロダクトミックスばかりを考えて自閉気味になっているところに、野口先生からふと海外の調査報告のURLの共有があった。
先生からのメールと言うことで嬉しくなって開いてみたらなんと英語。
しかも、どっさり英語。
普通だったらここでやる気をなくすところだ。
ただ、相手は世界に名を馳せる我が国コンクリート分野のトップアカデミア。
直々にお知らせいただいたと言うことはきっと何かあるのではないか。
決意をし、辞書を片手に英文を読んでいた昔を懐かしく、Google翻訳をワンクリックして中身を読んだ。
このところの翻訳の精度は非常に高い。
所々おかしいところがあっても、そこは生コンの知識がきちんと補ってくれるので問題はない。
ポイントは、こうだ。
"because usually the surface-to-volume ratio of concrete pavements is 10 times bigger than the surface-to-volume ratio of concrete elements in a building."
通常、コンクリート舗装の表面対体積比は、建物内のコンクリート要素の表面対体積比の10倍であるためです。
コンクリートの表面積/容積
以前から紹介しているように通常のコンクリート構造物(文中では建築構造物に限定されているが、橋脚、堰堤、トンネルなどあらゆる構造物も含まれる)の空気にさらされる部分は限定的だ。
よく先輩職員に言われた。
「目にみえる橋脚のコンクリートの倍以上が地中に埋まっている」
基礎構造物など重さを支えるためのコンクリートは大気に触れることなく埋もれている。
さらに、マスコンクリート。
CO2に触れる箇所は面状であり、√t則と言って時間(t)の経過に従ってCO2は表面から深部に向かって九州されることがわかっている。
つまり、コンクリートのCO2固定化に関しては何よりも空気中に触れる面積がものをいう、ということがわかる。
一方で、コンクリートそのものは大地を削り、汚し、蓋し、CO2を排出している。
ここでわかるのは、「なるべくコンクリートの容積を小さくし、なおかつCO2接地面を増やすことがCO2抑制に効果的」ということだ。
簡単にいうと、少しの容積のコンクリートでなるべく多くの表面積が有利、ということ。
MITによれば、通常の建築コンクリート構造物に比して、舗装コンクリートは表面対体積比で10倍という。
建築、或いは土木コンクリート構造物よりも、舗装コンクリート構造物の方がより効果的にCO2を固定化することがわかった、ということ。
じゃあ、どうなの?表面しかないコンクリート構造物、ポーラスコンクリート。
舗装に用いられるセメントが排出するCO2の実に5%を相殺しているという。
その舗装コンクリートの表面対体積比は建築コンクリートに比べて10倍。
すると、以下のような仮説が立てられるのではないか。
「通常のコンクリート舗装に比べて舗装に用いられるポーラスコンクリートの表面積(つまり、CO2固定化面積)はx倍であるため、舗装に用いられるセメントが排出するCO2の5・x%を相殺する」
(もちろん、セメント水和物の総量という限界があるため、単位時間あたりの比較になるはずだが)
透水性コンクリート(ポーラスコンクリート)舗装は、CO2接地面しかない構造。
⚫︎参考:ポーラスコンクリートの二酸化炭素ガス吸収特性と物性変化に関する研究
きっと、それに近い論文があるはずだと探していたら、それほど多くはないにしてもやっぱ見つけた。
太平洋セメントに在籍している小川さんという方の博士論文のようだ。
こういう国会図書館に所蔵されている書籍ってどうやって手に入れるのだろう。
これから、あれこれ、調べてみねばなるまい。
MITでも論じられているようにCO2固定化は供用時だけに関わる問題ではない。
期間満了して解体・撤去され、再生骨材として新たな役割を付された後でも固定化(中性化)は続く。
ただし、地中に埋められることで大気との接触が断たれた場合は固定化量も影響を受ける。
つまり、重要なのはいかに短期間で多くのCO2を固定化できるか、ということになる。
特に、雨の多い我が国では、コンクリート舗装のCO2固定化量も比較的大きいということがわかっている。
CO2吸収にこれほど有利な国土はない。
いやはや、すごいことになってきた。
ただでさえ、CCUを実装することで、セメント硬化体の中にCO2を収容することができる。
そのコンクリート構造物としてのポーラスコンクリート舗装(ドライテックなど)はさらにそこからより早くそのキャパシティ(中性化を許容できるセメント硬化体質量)分CO2を固定化することができるはずだ。
仮に、ポーラスコンクリートが用いてるセメントが排出するCO2量をオフセットすることができたとしたら。
世界にはポーラスコンクリート舗装を用いない根拠が絶滅する。
アスファルト舗装を推進する理由が根絶する。
あらゆるテクノロジーは統合されていく。
CCU(CarbonCureやblueplanet)もそう。
残コン由来の骨材利用ももちろん。
それらがポーラスコンクリートに統合された舗装は、「大地を削らない、汚さない、蓋しない、CO2を収容する」コンクリートとなる。
誰か、このテクノロジーの普及に異を唱える人がいたら教えてくれ。
今、そこで、施工されているその舗装。
今は許されているかもしれないが、「それを使うこと自体が恥ずかしい」時代がやってくる。
大昔、奴隷制度に誰も疑問を挟まなかったのと同じことだ。
今、当たり前に舗装をしていることに誰も疑問をさし挟まないかもしれない。
ただ、数年後には、「なんであんな舗装を使っていたのだろう」と猛省する時が来る。
なぜ、あんなにCO2を排出していたのか、と。
時代の動きはそれだけ早い。
宮本充也












