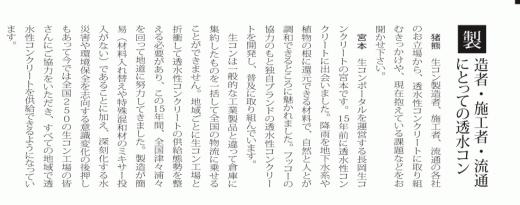2020/02/03
インターネットが拓く生コン新市場(セメント新聞)

業界メディアセメント新聞社で「インターネットが拓く生コン新市場」として透水性コンクリートの急拡大が座談会形式で紹介された。IT流通が拓く生コン新市場とは生コンの製造者、そして施工者にとってどんな意味を持つのか?
製造者・施工者・流通にとっての透水性コンクリート
右からセメント新聞猪熊夏子さん、エクスショップ加島雅子さん、宮本、記者の瓜生大輔さん、富士西麓ガーデン木川勇麿さん、東北レミコン佐藤大二郎さん。
今回は猪熊夏子さんがインタビュアーとなって座談会形式での紹介。
カーポート&透水性コンクリートの施工体験に集った人たちによる即席の座談会。
生コンポータルでは15年の歴史を数える透水性コンクリート。
そのコンクリートテックは降雨を地下水系や植物の根に還元できる。
自然と人が調和する世界への具体的なテクノロジー。
生コン一般の製品特性として「地産地消」が挙げられる。
半製品で1時間半以内に納品が原則となっているため一般流通(物流)に乗せづらいことが特徴。
そのため、地域ごとの生コン工場の理解が絶対必須となっていた。
15年間製造の簡便さを説明して回る努力や、深刻化する自然災害に対する意識変化もあり、全国供給体制が整いつつある。
そのことでIT流通との接続が実現した。
全国一物一価格(いちぶついっか:どの地域でも同一単価での流通)が実現。
それは製品の急拡大を意味する。
製造者にとっての透水性コンクリート
「透水性コンクリートは自社の特徴として打ち出しやすく魅力を感じました」
「新鮮さ・驚き・挑戦といった要素をもたらした」
(東北レミコン佐藤大二郎さん)
もちろん、新規需要開拓というのが第一の目的かもしれない。
人口減少に伴う生コン生産量の低迷。
発注官庁そして建設業界からの求めに応じて製造する生コンクリート。
それは決して自ら市場を創造する性質のものではない。
後追い。
建物やインフラが計画されてようやく必要とされる。
受動的な産業。
そこに、「新鮮さ」とか「驚き」「挑戦」といった要素は希薄になりがちだ。
僕が入職したばかりの生コン工場はまさにそんなだった。
JIS規格
鉄のルール。
はみ出すことは許されない。
1つの正解があって、そこからはみでたら落第者。
グレるしかなくなる。
内申点が下がる。
いい高校、いい大学に行けない。
いつしかできあがった四角四面な世界観。
そこにいる人たちにとって生コンは「生きるため」の手段。
家族を養うため。
糊口をしのぐため。
「楽しむため」とか「自己実現のため」なんて文脈はない。
そんな産業が果たして発展・成長していくだろうか。
まだ、若くいわゆる従来の生コンに染まっていない生コンパーソンを虜にする魅力が透水性コンクリートにはある。
佐藤さんはだからこそ自社の特徴として一昨年の夏頃から取り組みが始まった。
その実績は順調に増え続けている。
僕のところには全国の生コンパーソンから、
「ようやくお客様からちょこちょこ声をかけてもらえるようになった」(大分綜合建設九鬼智絵さん)
「ほぼ毎週出荷してますよ!」(毛受建材ダイソンこと大村貴史さん)
という声が寄せられるようになっている。
特に若手は閉塞する産業構造の底で自らの可能性を解放する機会を切望しているのだ。
そしてその機会としての透水性コンクリートがいよいよIT流通と出会った。
その意義はさらに増大していくことになる。
(その2:「施工者にとっての透水性コンクリート」に続く)
宮本充也