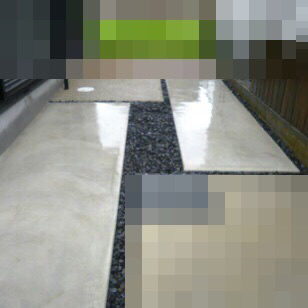2020/04/03
「滑りやすい土間コンに手すりをつける」手すり・コロナ感染防止・防滑(ノンスリップ)

歩行とは人間本来の行為だ。大地は何にも覆われていなかった。高齢者が土間コンクリートの上で足を滑らせあわや転倒という出来事に遭遇した方からのご提案。透水性コンクリートは人間本来の生活を取り戻すことができる。
「雨の日滑るから手すり」は問題解決策なのか?
雨の日土間コンは光沢を帯びて滑りやすくなる。
写真奥側の土間コンクリートは1年しか経過していないのに苔むしている。
特に北側など日が当たらず湿気やすい場所の土間コンはすぐにコケが生えてきて常に滑りやすく歩行しづらい。
こちらもよく見かける光景。
雨の日土間コンが滑りやすいから手すりを設置する。
透水性コンクリートは雨の日でも従来の土間コンのように光沢を帯びることがない。
そもそも滞水することもなく、表面は水を吸い込むための隙間があるため粗面だから滑りづらい。
建物の北側など常に湿り気のある場所でもコケが生えづらい。
安心して歩行することができる。
屋上屋を重ねるコンクリート産業からの脱皮
当たり前すぎて誰も意識すらしない、地面はコンクリートに覆われているという現実。
雨の日ぬかるんでしまい歩行に差し支える。
夏になると雑草が繁茂し草取りが大変。
だから舗装する。
人工物で覆われて本来水を吸収するはずの地面では水(自然)の支配が必要になる。
水勾配(傾斜)がつけられ、その先には排水設備が設置されて。
支配された水(自然)は河川、そして海洋に人為的に棄てられる。
貴重とされる水資源を人類は棄てている。
人工物「コンクリート」をつくるために山河は削られ細る。
すると少しの雨で河川は荒れ狂い大量の水が人の住む地域に押し寄せる。
人々の暮らしを守るため(自然を支配するため)にコンクリート護岸はさらに強化され、冠水を防ぐためのコンクリート排水設備もさらに強化される。
インフラが強化されればされるだけ山河は削られるコンクリートが大地に蓋をする。
⚫︎舗装
⚫︎排水設備
⚫︎護岸
は一見問題解決策のように見えるけれど、全体論で考えた場合抜本的な対策とは言えない。
自然と人が対峙するいたちごっこ。
とても、自然と人が調和しているものではない。
⚫︎手すり
一見転倒防止という意味では問題解決策のようにもみえるが、自然と人の関係性という本質から考えた場合これも抜本的な対策とは言えない。
そもそも、覆われていない地面に人々は暮らしていた。
雨の日に転倒しやすくなったり、苔が生えて足元を取られるような地面ではなかった。
自然と人が調和するコンクリートテック「透水性コンクリート」
かといって今更ユニクロやスタバのない世界に戻ることはできない。
戻れると主張する人がいるならどうぞ山奥でひっそりと暮らしててください。
僕はそんなのは嫌だ。
今更舗装のない世界に戻ろうなんてのは非現実的だ。
暖かい部屋でHuluを視聴したいし、ワンクリックでなんでも届く現代の利便性を捨てたくはない。
現代の現実を踏まえて先端のテクノロジーで2分法を超越する。
環境コンクリート「透水性コンクリート」を採用することで雨水は大地に吸収される。
滞水しないから滑りやすくなるということはない。
コケ・カビが生えづらい環境を維持することができる。
そもそも、水を吸い込むための隙間(空隙)のおかげで表面は染めんだからノンスリップ(防滑)効果もある。
水を誘導するための傾斜(水勾配)もないから足元を取られることもない。
⚫︎ぬかるみ
⚫︎雑草
⚫︎水たまり
を解消するために土間コンクリート(透水性コンクリート)で舗装しても、手すりに頼ることなく人間本来の歩き方で歩くことができる。
手すりをつけないことで結果的にコロナウィルスの拡散防止にもなる。
こんな視点を与えてくれた方がいた。
その方は雨の目の前を歩いていた歩行者が雨で濡れた土間コンに足を取られてあわや転倒という場面に遭遇して上記観点に至ったという。
年中透水性コンクリートのことを考えている僕にもない視点だった。
人類の繁栄という名の未来世代からの搾取。
後50年で石灰石(セメントの原料)は枯渇すると言われる。
これからもまだ僕たちは大地を削り、汚し、蓋し続けるのだろうか。
あまりに当たり前で意識することすら無くなってしまった「コンクリートで大地に蓋をする」という行為。
だが、今のように大地が埋め尽くされてしまったのはほんのここ数十年の出来事。
たった数十年で僕たち人類は自然を忘れてしまった。
いつしか自然は支配する対象のように思いあがってしまったようだ。
歩行とは人間本来の根源的行為。
人類の思い上がりを脱し、自然と人が調和する世界を取り戻すためには、縄文時代の生活様式に戻るような原理主義ではなく、先端テクノロジーをきちんと見出し普及させていく努力が必要だ。
本質を見失うことなく産業人としての使命を果たしていきたい。
宮本充也