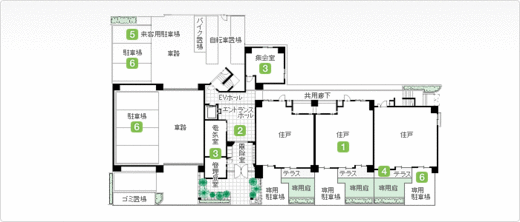2019/11/09
「生コン屋をもっと身近に」営業不在の業態
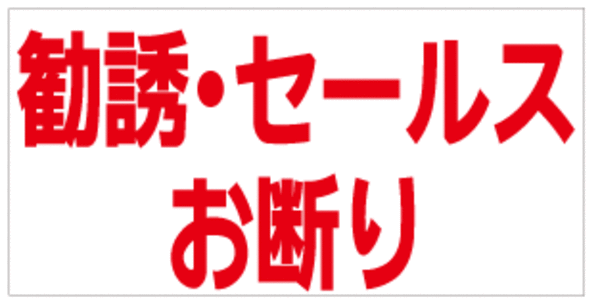
普通のビジネスと生コン屋の違うところ。
「セールス部門がない」
「?」
と感じた人は普通の感覚。
生コン業の基本フォーマットは「営業マン不在」というのは、
67歳の生コン産業にとって大きな特徴。
普通ありますよね、営業部とかセールスを担当する機能。
こうなった背景には、協同組合という存在がある。
生コンという半製品は1時間半(1.5時間の壁)以内でしか売ることができない。
そして、どういうわけか、販売協同組合というカルテルが公に認められているので、
割決
と呼ばれる手法でご当地生コン組合が一元的に販売店やゼネコンと価格交渉して、
納入する工場が自働的に決まっていく。
普通のビジネスでは当たり前の、
・僕の方がすごいです
とか、
・相手のどこそこはうちよりもだめです
・この製品を買った方がお得です
みたいなプロセスは皆無で、
「こちらの工場から買っていただくことに決まりましたのでお買い上げください」
という形で売り買いが成立するケースがあるくらいだ。
つまり、セールスお断り以前に、
「安心してください、セールスしませんから」
となっている。
とまあ、ここまでは生コン産業の特徴をありていに紹介したわけだが、
そんな生コン業界に僕は16年ほど前に入職し、
当時から「斜陽産業」ど真ん中、下りのエスカレーターにのっちゃったよ、
って実感があったので、仕方なく(?)新規事業を始めるきっかけとなったのが、
「水たまりのない駐車場」→ドライテック
だった。
当時のぼくの感覚は、
「水を透すコンクリートすげえ、絶対売れる」
というごく安直なものだったのだけれど、
それまでは1.5時間の壁の中で生コンを創業するしかなかったので、
外の世界に「水たまりのない駐車場」を売り歩くことができるのは、
本当に本当に楽しい経験だったことを覚えている。
今日も営業してたんだけど、当時から設計事務所や造園会社が主な営業先。
行く先々で面白がられた。
「生コン屋が営業に来たのは初めて」
好奇の目を向けていただける方も少なくなくて、
だいたい話が弾むケースが多い(僕の営業トークはいけてません)。
今日も改めて実感したんだけど、
生コン屋こそ外の世界に向けて発信することで大きなチャンスがある業種はない。
設計事務所に営業に行くメーカーは多い。
そして、彼らは多くの競合他社と比較される中で自らの価値を伝える。
例えば、透水性インターロッキングブロックという製品がある。
(※つまり水を透すブロック→水たまりのない舗装)
これを扱っているメーカーや販売店はそれこそ、死ぬほどある。
彼らは自社の製品が素晴らしいことを伝えるために、
・意匠(色とか模様)
・機能(透水性能や保水性能)
・経済性(価格)
がいかに秀でているかを多くの競合に晒されながらプレゼンする。
今日も設計事務所のクライアントの方に教えてもらったんだけど、
「そもそも、透水(水を透す)製品はインターロッキングブロックくらいしかなくて自由度が低くてつまらない」
とのことだった。
もう、ぶっちゃけインターロッキングブロックだとコモディティ化しちゃってるようだ。
そこに、生コン屋が現れた。
(Google画像検索で得た図面)
共同住宅には共有部と専有部という区切りがある。
緑色のスペースは公共の場所ではなくて、住戸に専用に帰属したスペース。
ここが設計者の頭を悩ませる場所だそうだ。
この場所は、隣地に接している場合が多く、
降雨が敷地外に流出してはいけないことになっているため、
排水計画(水勾配の設定や排水施設→U字溝や集水桝の設置)に苦慮するという。
それを解決するのはこれまで、
透水性インターロッキングブロックしかなかった。
そこに、普段営業をすることがない生コン屋がふと現れた。
インターロッキングブロックではない、
「水を透す生コンがあります」
とても驚いていただいた。
自由度が増えたということだった。
10年以上、「生コン屋でありながら営業をする」ということを続けているが、
一度も、設計事務所で生コン屋を見たことがない。
つまり、大海原に1船も浮かんでいない、見渡す限りブルーオーシャン。
こんなに楽勝(?)な営業があるだろうか?
こうした文脈から言えば、生コン屋は1.5時間の壁の外へ船出すべきだ。
1.5時間の中にもはや無限大の可能性などないのだから。
そういう意味では生コン屋の情報発信には無限大の可能性が眠っている。
GNN元気な生コンネットワークは期せずしてこうした文脈に沿うアライアンスに成長した。
「生コン屋をもっと身近に」
縦割りの脈で埋もれていた生コン屋というリソースの流動性を高めることで、
ドライテックを始め、多くの価値が生まれていく。
いよいよ明後日に迫った、
はそういった意味で業界内だけでなく、広く世間一般に対して発信する機会。
福岡陥没事故や、豊洲市場の問題などで、一躍世間の衆目に晒される生コン。
水の次に流通する材料はどんな人たちがどのような思いで供給されているのか。
僕たちの本気を見ていただける良い機会としたい。
宮本充也