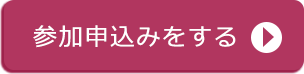2020/11/16
【長野】「なんで《寒冷地こそ》透水性コンクリートなの?」竹花工業 小諸工場・エクスショップ

長野県佐久市。施主がネットで見付け、エクスショップに「ドライテックにしたい」と希望を寄せる。同地は-15度まで気温が下がる環境であるため、凍上対策として300㎜の根伐りを実施(凍結深度までの土壌改良)。下層150㎜で下地、上層150㎜をドライテックという仕様が特徴的だ。(二見メンバー報告)。
製造:竹花工業 小諸工場(掛川直樹)、施工:エクスショップ(33m2、150㎜厚・2層施工、6名、約2時間40分)。
寒冷地こそ透水性コンクリート《ドライテック》
施工Before。
採用理由は至ってシンプル。
お施主さんから「ドライテックにしたい」と希望が寄せられた。
商品名そのものがもう完全に一人歩きをしている証拠だ。
ここまでくるとなかなかに感慨深い。
そして、プレートコンパクタ30kgタイプは特注で幅広タイプとなっている。
今回の施工のために、新しく幅広プレートを特注。
約900×700(価格はまだ出てきていないそうだ)
ドライテック製造の竹花工業 小諸工場さんはもうこれまで何件も製造経験があり普通の生コンのように注文をすることができる。
担当は掛川直樹さんまで。
施工者はドライテック未経験者だったため2層打ちの下層で施工の流れを全体に周知・練習。
バタ角で高さを取りながら、平らに敷き均す。
仕上げの上層は、両サイドの型枠をガイドに、定規で切って平滑度を確保。
施工After。
33m2の面積を150㎜厚を初施工ながら6名で約2時間40分で仕上げてしまった。
以下は、施工に携わった皆さんの生の声。
「土間コンよりも楽でいいね」
「思ったよりも簡単にできた」
「また別の現場でも採用しようかな」
寒冷地こそ透水性コンクリート《ドライテック》の理由。
北海道や長野県の一部地域など極寒の地域は新しい材料に対して保守的な傾向がある。
ただ、このところわかってきたのは、「寒冷地こそ透水性コンクリート」。
なぜか?
初期凍害のことを考えると、「仕事は早く終わる方がいい」というのが答え。
従来の土間コンクリートを例に取ってみよう。
敷設、均しまでは同じだが、そこからがまるで違う。
⚫︎余剰水の乾き待ち
⚫︎金鏝で何回か擦る
それぞれで下手すると3時間は見ておかねばならない。
だから、施工はまだ環境が凍結しているような早朝から始めねばならない。
日がさして暖かいのはほんの数時間。
一転翳り始めつるべ落としのように日が落ちる。
ぐんぐんと下がる気温の中給熱養生をしながらせっせと仕上げ。
従来の土間コンクリートは1日仕事になってしまうため初期凍害を予防するための養生も嵩むし作業も多い。
一方の透水性コンクリート。
こちらは、従来の土間コンクリートに比べて、「新しい土間コンクリート」とでも呼ぼうか。
何せ、GD賞金賞(経済産業大臣賞)を獲得し、世界的巨匠隈研吾にも見出された土間コン。
押しも押されぬ日本が誇る透水性コンクリート《ドライテック》は新旧で言うと、新土間コンクリート。
その最大の特徴は、「仕事が早い」。
初施工でしかも2層打設という特殊条件であっても、33m2をたった2時間半で終わらせてしまった。
その理由が、「余剰水」「金鏝仕上げ」がない、ということ。
プレートで締め固めておしまい。
これが、最大の強み。
寒冷地でも力強く施工実績を伸ばす透水性コンクリート《ドライテック》。
もしかしたら、雪国で最も見出されるのかもしれない。
冷え込んだ暗闇で金鏝仕上げとかしてたら、「だっせぇ、まだ土間コンを金鏝仕上げしてるよ」と嗤われてしまう日がやってくるのだろう。
もう、今ですら、「ドライテックできません」なんて言ってる施工者はオワコン気味になりつつあるのだから笑。
まだ、万が一やったことも聞いたこともないなんて施工者がいらしたら早めのオンラインセミナー受講あるいは見学会参加をお勧めする。
一度受講さえしてしまえばきっと自身もつくはずだ。
生コンポータルでは施工者であるあなたが「ダサい」なんて言われないことを切に願っている。
宮本充也