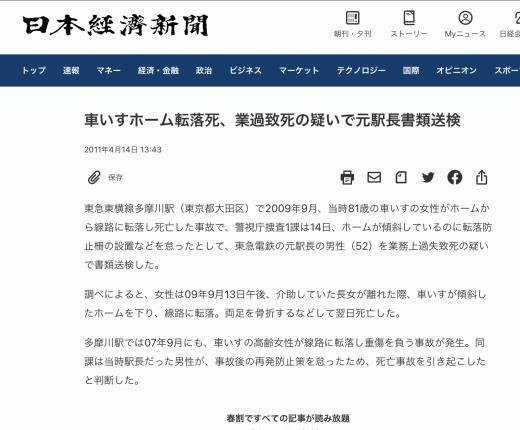2021/04/28
《提言》「駅ホームの傾斜(水勾配)による車椅子転落の根本解決について」

出張で訪ねた福井県武生駅に表示されている看板をみていてはたと気づいた。確かに聞いたことのある駅ホームの傾斜(水勾配)による車椅子転落という痛ましい事故。大方の意見は、「転落防止柵の設置」のようだが、もっとあるだろ、その前に。
転落防止策設置の前にやれること
出張で訪ねた福井県武生駅ホームの舗装。
ふと見ると、こんな看板。
「ホームに傾斜がありますご注意ください」
堂々と言って退けている。
なぜ、傾斜があるのか。
それは、水勾配と言って、雨が降り込んできた場合排水するために傾斜が必要。
エクステリアの土間コンでも散々この点を論ってきたが、水勾配とは何もエクステリアなど家周りの話にとどまらず普遍的な現象。
水が高いところから低いところに流れる以上、永久についてまわる問題のようだ。
ふとインターネットで「駅ホーム」「傾斜」「車椅子」と調べるとわんさか出てくるではないか。
(出典:https://www.nikkei.com/article/DGXNASDG1400R_U1A410C1CC0000/)
「ホームが傾斜しているのに転落防止柵の設置などを怠ったとして、東急電鉄の元駅長の男性(52)を業務上過失致死の疑いで書類送検」
もちろん、起きてしまった事故は痛ましいのだけれど、書類送検で終わらせるのも根本解決ではないような気がする。
そもそも、転落防止策の設置が課題解決策として認識されているようだが、東京のような大都市の地下鉄会社ならまだしも、地方の私鉄(例えば僕が住む街の鉄道会社、伊豆箱根鉄道)ではそんな大仰なものを設置できるとは思えない。
東京オリンピック2020を迎える現在ですらクレジットカードすら使えない私鉄なのだ笑。
転落防護策など夢のまた夢。
「ホームに傾斜があります」
程度の注意喚起では単なる言い逃れ、「ちゃんと注意喚起してましたよ」でしかない。
そもそもが、「駅のホームに傾斜をつけない」という世界を生み出すことが求められる姿勢なのではないか。
(地球に蓋しないコンクリート:https://www.nr-mix.co.jp/dry_tech/)
ポーラスアスファルト、あるいはポーラスコンクリート・ドライテックという根本解決策
人類は忘れている。
駅員さんも忘れている。
2009年に起きた痛ましい事故の他にも、ベビーカーなど「タイヤ」がついたものが往来する駅ホームが傾斜しているのは望ましい状況ではない。
傾斜(水勾配)が必要のない舗装には、2種類ある。
ポーラスアスファルト、並びにポーラスコンクリートだ。
部材内部に無数の連続した空隙が存在するため、その穴を伝って水が表面から部材内部に浸透していく。
つまり、これらマテリアルを駅ホーム舗装に採用するだけで、「ホームに傾斜があります」と言わなくても済むようになるのだ。
アスファルト、コンクリート、それぞれのメリットデメリット
透水性コンクリートドライテック講座 #1 コンクリートとアスファルト
ポーラスアスファルトのメリットとして挙げられるのは、即時交通開放。
コンクリートと違って、「冷めたら固まる」がアスファルトなので、施工直後、温度が50度を下回ればすぐに交通開放(その上を歩行)できる。
ただし、ポーラスアスファルトに関してはその温度管理が困難を極めることが知られている(デメリット)。
ただでさえ通気性のある材料となっているため、冷めやすい。
そのため、施工は人力施工をなるべく避けるように励行されているくらいだ。
駅ホームのような制約の多い現場条件の場合機械施工はなかなかしにくくその点が阻害要因となりやすい。
また、アスファルト全般に言えることだが、耐久性はコンクリートの比ではない。
樹脂・石油製品であるため、数年の供用でポーラス(空隙)が潰れてしまい透水性が失われる場合がある。
ポーラスコンクリート(ドライテックなど)のメリットは施工簡易性と耐久性。
女性2人などDIYでも広く用いられているほど敷居の低いマテリアル。
豊富なDIY施工実績は生コンポータルのDIY施工事例からも多数閲覧することができる。
(DIY施工事例:https://www.nr-mix.co.jp/dry_tech/diy.html)
一方、デメリットとしては、「水和反応が硬化のメカニズムであるため、交通解放までの時間がかかる」というのがある。
エクステリア駐車場土間なんかもそうだけど、「車が乗り入れるまでは中5日空けてくださいね」というあれだ。
夜のうちにドライテックを施工して、翌朝から人々が問題なくその上を歩ける、というわけにはいかない。
そのため、施工面をベニア板などの簡単な養生材で保護することなどの措置が必要となる。
いずれにせよ、駅ホームに傾斜はいらない。
すでにソリューションはあるのだ。
あとは、知ってもらうだけ。
この「知っている」というたったそれだけのことが世界の景色をどのようにでも規定することができる。
生コンポータルの使命は「生コンをもっと身近に」することでソリューションを広く世間に認知してもらうこと。
痛ましい事故がこれ以上続かないように。
知ってもらう努力をすることは僕たちものづくりのラストワンマイルの使命だと思う。
宮本充也