2019/01/19
「アスファルト舗装から200年前の地面へ...」【茨城】の地に透水性を取り戻せ!|ドライテック
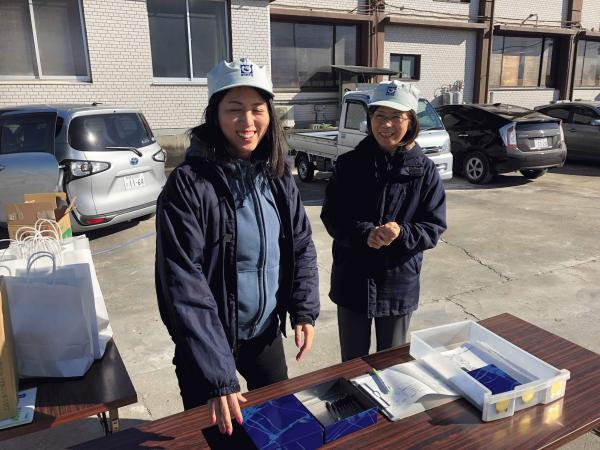
茨城県つくば市の大里ブロックで開催されたのは第4回透水性コンクリート施工見学会。近隣の発注期間や工事業者さんが30名も集まり環境への意識を新たにした。
もう安易に【アスファルト】はやめよう
というわけで始まる生コン見学会。近隣発注期間や工事関係者。中には埼玉県熊谷市からのご参加もあった。
寒い中溢れる笑顔で来客を迎える受付のお二人。
施工箇所をぐるりと取り囲む見学者の方々。
施工を受け持つのはプロではない、普通の生コン工場の人たちの手による透水性コンクリート。順調に進む。
歩掛りはどうするの?
行政の担当の方からの質問。
とても興味・関心を抱いていただいたようだ。
0.5m3という小規模小ロットから注文できる。
アスファルトよりもさらに身近。
今日注文しても届く。
地元企業生コンならではのフットワーク。
「発注したい場合に歩掛りは、コンクリート舗装工?それともアスファルト舗装工?」
そんな質問をいただいた。
たしかに公共・行政などの発注スタイルは、
歩掛り(ぶがかり、ぶがけ)
といって、全ての費用がまるっと含まれた様式で発注されることになる。
歩掛り
歩掛りとは、建設工事の積算の際に使われる、職種ごとのの労務単価に当該作業に従事する時間を乗じたもので、工事費用の根拠となるものである。
国土交通省が公共建築工事標準積算基準に歩掛りを示している。
(施工の神様から引用)
今はほとんど民間工事での普及がメインになっている。
だから、こうした質問はとても新鮮だった。
民間・公共問わず採用されてこそ。
日本の地面の常識が変わる。
200年前の地面を回復する。
透水性コンクリート舗装工という歩掛りができるために
しばらくは、3者見積もり。
3者以上の企業からの見積もりを調達して、
公正な競争の結果採用されるスタイルが必要となる。
施工のプロでもない僕たちが勝手に、
「これはアスファルト舗装工と同じ歩掛りを採用してください」
そんなわけにはいかない。
だから、個別の案件で個別の見積もり調達が必要になるだろう。
さらには材料単価も調査会が調べる程度の流通実態が必要になろう。
2019年は透水性コンクリートが標準になる元年。
今、手元に来ている見込み・引き合い案件だけでも昨年までとの比ではない。
2020東京五輪も控えている。
ますます時代の要請が【透水性コンクリート】に寄ってきている。
そんな実感がある。
もはや、副産物ではなくなったアスファルトの代わりに。
地道な普及活動の先に歩掛りが整い。
アスファルトのように当たり前に採用されるようになれば。
もはや、アスファルトは産業副産物ではない。
石油精製の過程で出てくるゴミじゃない。
ゴミで日本の地面を覆う必然性は無い。
一方、コンクリート舗装。
石油製品と違って「普遍」「耐久性」が売り。
一度舗装をしてしまえば、その舗装は半永久。
恒久的な舗装。
さらに、水を透す。
日本の地面は200年前の何にも覆われていなかった地表を取り戻す。
茨城の地面をこれ以上汚すのはやめよう。
それができるのは、建設、生コンに携わる僕たちだけ。
口だけじゃないサステナビリティの実現に。
生コンでいいこと。
茨城でも始まる。
宮本充也













