2017/01/31
「クラウドワークスに学ぶ」 土間コン・水たまり・コモディティ化
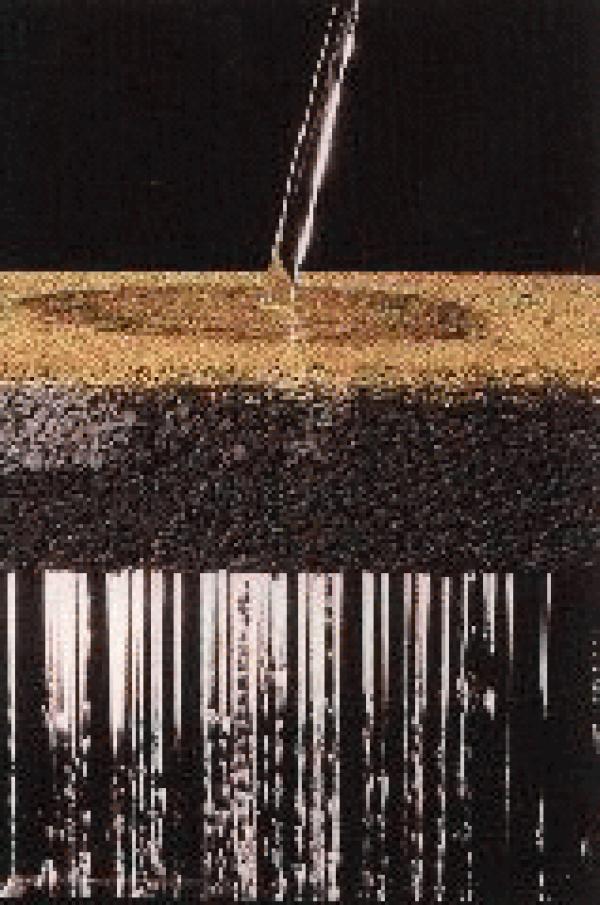
例えば、
「住宅」と「生コン工場」
が解りやすい。
「住宅」→需要
「生コン工場」→供給
いずれもごく近所に存在している。
とある街(東海地方)に建てられる住宅の基礎(生コン)は、
北海道地方の生コン工場から運ばれることはあり得ない。
必ず近所の生コン工場から生コンが供給される
これが、物流となる。
情報の流れはこれとは全く異なる。
「住宅」という需要に対して全国区で展開する住宅メーカーが請ける。
とある街における住宅という需要に対して、
東京など本店に伺いをたてる形で情報は集約(管理)される。
生コン供給については、
組織のルールに基づき取扱い商社(全国区)に発注され、
当該地区を担当している担当者が生コン供給について責任を持ち、
とある生コン工場(当該地区協同組合)に指示があり、
供給が実際に行われる。
物流はほぼ隣
歩いていけるくらいの距離だとしても、
需要の管理の流れ(商流と言ってもいいかもしれない)は、
一度中央(本店)に集約され再配分される形で供給に齎される。
需要と供給の実際の距離が隣通しであるにもかかわらず、
管理するためのルートは非常に遠い。
情報は本店から地方の生コン工場へ降りていく形をとる。
これが、現在の社会・経済の仕組み、つまり、
多重構造
となっている。
これは、IT(情報革命)以前のリアルだった。
モノが供給される前には必ず情報が通る。
生コン(供給)が供給される前には住宅(需要)ニーズ(情報)が管理されるべきで、
その情報を管理する手立ては、
回覧板方式
つまり、いったん最上位(本店とか国家とかトップライン)に集約され、
順次降ろしていくという仕組みが有効だった。
・マッチング
・シェアリングエコノミー
IT以降、回覧板方式はなりを潜め始めている。
個人や中小法人が自ら情報を発信する手段を持った。
一々情報を最上位に吸い上げることなく、
ボトムラインで互いに意図した情報を発信する時代となる。
(LINE、Facebook、Twitter等)
例えば、一昨年IPOで注目されているクラウドワークスは興味深いビジネスモデル。
個人というリソースの活用方法はIT以前では、
組織(大企業)に属する
をおいて他になかった。
個人という需要も供給もそして情報もいったん組織の理論でトップラインに集約され、
組織構造を降りていく形で個人に指示(発注)がなされていく。
社蓄
なんて言葉はその揶揄となる。
個人のリソースに光を当てる。
ボトムラインにある個人や法人(中小企業)というリソース(需要や供給)を、
多重構造を取り払い直接結びつける
ことで、不要な中抜き(富の搾取)を避けるという試み。
「住宅」と「生コン工場」
で置き換えると、
実は隣同士の需要と供給
を、ダイレクトに繋げることができれば、
得られる富は必ずあることがうかがわれる。
どこかの地方に埋もれている生コン工場の持っているリソース、
(たとえば、水たまりのできない駐車場)
実は隣にある需要、
昨年結婚し子供もできて今のアパートが手狭になりました。いよいよ夢のマイホームを建てようと思っています。そして、念願だった車いじりを日曜日自宅の駐車場でやれればなと思っています。(※水たまりのできない駐車場が有効だとして)
に対して、
供給者(生コン工場)が有効なソリューションを提供するために、
既存の情報流通機構(多重構造)であるととてもじゃないけど遠すぎて届かない。
需要と供給が直接に結びついたらすぐに納得
が、多重構造で希釈され共感が得られなくなり、
コモディティ化した普通の土間コンが組織の理論で供給されることになる。
つまり、独自の価値が流通の過程で消えてしまう。
全世界で埋もれているリソースに光が当てられる時代。
僕たち生コン工場の業界環境もまさに、
ICT、IoT、i-Construction、AI
など、横文字かまびすしい。
「言われたこと(生コン練っとけ)だけをやってりゃいい時代」
はもう終わりかけている。
INDUSTRY 4.0
モノづくりのパラダイムもここで大きく変革する。
もちろん、生コンもその例外ではない。










