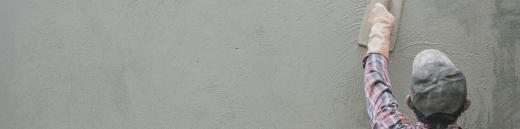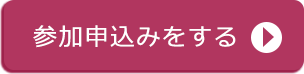2020/06/11
「これからは土木も見た目の時代」ジャンカ・色合わせ

某地域。橋脚の脇の下部分に発生したジャンカをはつりとり、色合わせを施した。土木構造物の場合は全て打ち放しコンクリートであるため現場では出来型管理には細心の注意が配られる。それでも起きちゃうトラブルに転ばぬ先の杖「色合わせ補修」。
土木構造物(コンクリート)は全て打ち放し
特殊補修「色合わせ」と聞くとほとんどがおしゃれな建築の打ち放しコンクリートを思い浮かべるかもしれない。
こちらの現場はとある土木現場から呼ばれて施した色合わせ。
人の住むところ(建築)以外は全部土木の領域。
ダム、擁壁、橋、護岸、隧道、あらゆる全ては土木と呼ばれる領域。
生コンクリートの需要を建築と二分する領域。
それが、土木。
(厳密には舗装、造園などの分野でもコンクリートは用いられているがおよそは建築と土木で用いられている)
建築は「仕上げ」が前提にある。
塗り壁やクロスなどコンクリート構造をそのままではなく被覆することで見た目を機能としている。
(老舗塗り壁メーカーフッコーのHPより)
多彩な色やテクスチャを「選ぶ」ことができるのは建築構造物の特徴。
一方で、土木。
どちらかというと無骨なイメージがあるのではないか。
それもそのはず、土木構造物は見た目というよりも、耐久性や強度ばかりが要求される。
最近話題のインフラツーリズムという観点も出てきてはいるものの、基本的には土木構造物は人の暮らしを縁の下で支える存在。
なるべく目立たない方がいい。
そのように考えられ来た。
そのため、建築で発展したような「意匠性」はそれほど要求されない。
建築の設計事務所にはなんとなくチャラいイメージがつきまとう一方、土木コンサルはなんとなくむさいと思うのは僕だけだろうか。
(あ、多くの方々を敵に回してる??)
むさい、ではなく、硬派とでも言っておこう。
そんな土木構造物は塗り壁やクロスでコンクリート表面を被覆することはない。
建築と違って土木は「常に打ち放しコンクリート」。
仕様書には「見た目」についての要求事項はない。
ただし、監督官の目にはくっきりと写るのである。
そのジャンカ、コールドジョイント、ひび割れ。
そう、出来型管理が不行届だったことの印としての施工欠損。
土木こそ必要とされる打ち放し色合わせスキル
打ち放し色合わせは15分のセミナー受講で手軽に身につけることができる。
受付はこちらから。
今日も含めて毎日オンラインセミナーは15時から開催されている。
もしもあなたが土木に携わる人だとしたら、ほんの15分が今後の土木ライフを激変させる。
これからは土木も見た目の時代
チャラいは建築の専売特許ではない。
土木コンサルがなんだかすかした感じで髭はやして現場に颯爽と登場したっていいじゃないか。
コンセプトという言葉を連発したっていいじゃないか。
「ジャンカ(施工不良)はね、君。神様からの偶然の贈り物なんだよ」
と血迷って現場監督を困らせたっていいじゃないか。
「打ち肌が気に入らない」と言って安藤忠雄ばりに周囲に迷惑をかけたっていいじゃない。
これはらは土木も見た目の時代。
そんな時代のエチケットとして。
「生コンでいいこと」打ち放し色合わせは今や誰もが気軽に施工できるスキル。
宮本充也