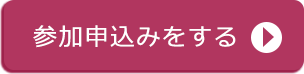2021/01/02
【長野】「《住宅基礎としての問題はない》では通用しないコンクリートコンクリート《美》というニーズ」

長野県の現場。住宅基礎立ち上がり部分の左官補修部分の色合わせ。住宅基礎は露出している部分を左官等で仕上げる場合もあるものの、その多くはむき出しのコンクリート、つまり「打ち放しコンクリート」。家の土台・基礎としての性能に影響はないものの、一生に一度の買い物ということで気にされる施主は多い。
「性能に問題はありません」とは言われたけど・・・
Beforeはコンクリートの充填不良箇所に補修用モルタルを埋めたもの。
実際に、性能に何ら問題はない。
むしろ、補修用モルタルの方が強度も耐久性も秀でている場合が多いため、より性能は期待できる。
さて、住宅基礎に要求される性能とは何だろう。
一生に一度の買い物をするお施主さんにとっては短期間に考えなければならないことは多すぎる。
一方、住宅を提供するハウスメーカーや工務店は年中家や建物のことばかりを考えている。
よく僕が引用する例え。
「結婚式場にとっては年間数十、或いは100組以上の結婚式。一方のカップルにとっては一生に一度の晴れ舞台」
ここにある溝。
これは、どうにも埋められない。
カップルからは、結婚式場のちょっとしたことでも、目につくのだ。
プロからしたら、「え?そんな些細なこと?」みたいなことでもめくじらを立てるのだ。
怒ってはいけない。
今回もそんな案件。
「基礎としての性能に問題はありません」
事実、その通りだ。
生コン打設の前にはきちんと配筋検査が行われ、所定の鉄筋量が確保されている。
そこに、所定の強度(伝票と、その後の強度試験で確認されている)の生コンクリートが打設されている。
所定の養生が行われている。
型枠を外したら、そこには施工上の不備である「ジャンカ」「ピンホール」などの充填不良が見られた。
(ジャンカ:https://yotubanoclover.muragon.com/entry/461.html)
(ピンホール:https://images.app.goo.gl/oLEdeRGJrPKjxYhQ8)
でも、大丈夫。
所定の補修方法できちんと補修され、要求される強度や耐久性は保全されている。
家としての性能に全く問題ありません。
こうした説明が続く。
専門家である僕だって、その説明に異論を挟めない。
でも、現実はそうは行かないのだ。
「あたしは見た目も買ってるの!」
住宅基礎の多くはむき出しのコンクリート、つまり「打ち放しコンクリート」の現実。
「土台の見た目なんて言われたって困るよ!。そもそもの役割は強度と耐久性なんだから」
は、大昔の土木屋の発想。
今や、その手の理屈は通用しない。
もし、通用していたのなら、土間コンの色むらやひび割れだって問題にならないし、あちこちの現場で炎上したりしない。
コンクリートの性能「強度」「耐久性」以外の領域のソリューション「色合わせ」。
結婚式場の例を引くまでもなく、プロの理屈は現代通用しなくなっている。
納品前にあんまり「免責事項」としてあれこれプロの理屈を主張するのは得策ではない。
そんなことしていたら、他のプロに案件ごと持っていかれる。
「やる気なさそう」という印象で発注者・施主から選ばれない、厳しい現実。
事実、僕たち生コン製造者だって、性能を謳っているのは「強度」。
「27N/mm2出ます」
と保証して、もしでなければ、その時は責任を取る。
(取り壊しの費用を捻出したり云々)。
施工者だって、耐久性(鉄筋量とかかぶり厚さ)を保証している。
それに満たない場合は責任を取る。
そして、現代は、それを当然とした上で、「見た目」「美しさ」をも要求される時代が到来している。
無骨なイメージがつきまとう建設・コンクリートの分野にも、見た目が要求されるようになったのだ。
コンクリート実務に携わっていると、こうしたこれまでに想定していなかったトラブルに巻き込まれる施工者(ハウスメーカーや工務店、エクステリア外構業者)からの問い合わせを多くいただく。
コンクリートの見た目のこと。
壁、土間、あらゆるコンクリートの美しさに関わること。
生コンポータルの「生コンでいいこと」は、この領域でもすでに15年近い経験を有している。
⚫︎参考記事:コンクリートの見た目問題ソリューション施工事例
多様化する建設・コンクリート周りのニーズ。
時代を捉え、市場と顧客が要求することを用意するのも、僕たちプロの役割。
資格試験に出てくることばかりで理屈をこねるのではなく、顧客が何を求めているかを探る感性が重要になったのだろう。
これからは、理屈よりも感性、共感の時代なのだと思う。
そして、この技能は何も特殊なものではなく、少しのやる気さえあれば「たった15分で習得できる」代物でもある。
要は、いかに顧客に寄り添い努力を惜しまないか、だけがプロの仕事を規定するのだと思う。
プロ施工者(上級DIYer)向け、無料セミナー申し込みはこちらから。
宮本充也