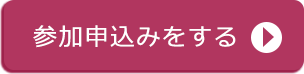2021/01/05
【愛知】「コンクリートを制するものは、エクステリアを制する」

愛知県の現場。GL(グランドレベル)付近に打ち継ぎに近いムラが発生したため色合わせ補修しました。外構擁壁。「エクステリアのコンクリートで厄介なのは土間コンだけ?」。そんなことはない。仕上げをしないコンクリート「打ち放しコンクリート」はあらゆる場所で見た目の問題を引き起こす。
エクステリアの打ち放しコンクリートは要注意
エクステリア・外構工事でももちろん、「水の次に流通する材料」生コンクリートは用いられる。
家など建物に用いられる場合と異なり、そのコンクリートは「素地がそのまま見える(打ち放しコンクリート)」であるケースが多い。
それも、エクステリアは外側に向けて設置される。
つまり、家よりも先に人目に触れる。
⚫︎参考記事:土間コンクリートの色むらについて
(※とても真摯な施工者の方のHPを見つけた。ご本人はお詫びしているが、「色むら」の原因はいまだに完全には究明されていないものだ。これは、土間コンクリートの運命といってもいいような現象で、誰も悪くない。早く、この因習を打破すべきだと思う)
(出典:https://con-rep.com/news/youheki1)。
エクステリアは生コンから逃げられない。
エクステリアに従事している人で、コンクリートを触ったことのない人はいない。
「水の次に流通する材料」生コンクリート。
あらゆる分野で、あらゆる施工者との接点を持つ材料。
(出典:https://www.garden.ne.jp/index.php?action=public_static&path=showcase-explanation/painted_wall.html)。
例えば、写真のように仕上げが指定されている場合は問題にならない。
仮に色むらや補修痕が発生してしまっても、適切な処置の後お化粧しちゃえば見えなくなるから。
でも、隠せる時ばかりじゃない。
世のエクステリアのコンクリート構造物はおよそ素地が丸見え、打ち放しコンクリート。
土間コンも土間コンクリートの色むらについてでも紹介されているようにとかく炎上しがち。
真摯な施工者と、お施主さんの間をギクシャクさせてしまいがち。
それが、コンクリートの運命。
そして、そんなコンクリートの運命からエクステリアは逃れることはできない。
そんなエクステリアシーンでドライテックが重用されるのも、「色むらが出ない」「ひび割れが見えない」という見た目の機能によるところが大きい。
エクステリアに携わるのであれば、コンクリートの適切な知識を身につけるべきだと僕は思う。
これまで、エクステリア界隈の方々と接してきて、「コンクリート技士」のようなコンクリート関連資格を有している人に一度もお目にかかったことはない。
これは、縦割りの弊害だと思う。
もっともっとエクステリアはコンクリートに関心を持つべきなのだ。
(逆のことを言われないように僕は「1級造園施工管理技士」の勉強をちゃんとやっている)。
コンクリートは怖くない。
適切な知識がありさえすれば、施主に対してしどろもどろな対応をしなくても済む。
コンクリートにはひび割れは発生するし、色むらも出るもんなのだ。
その上で、さらに色合わせ補修という技能を身につけよう。
もっと詳しく知りたい人は無料のWEBセミナーでより高度なスキルを習得できる。
今話題のドライテックの話も聞ける。
エクステリアは、「土木」「建築」「コンクリート」といった科学分野から孤立しているように思う。
なんとなく、知識がチープなのだ。
メーカーの言いなりというか。
「とりあえず、その辺の部品を持ってきて組み立てました」感が否めない。
主体性がない。
科学的背景が乏しい。
学会がない。
散々言わせてもらってるが、実際僕が感じるエクステリア業界の印象だ。
何もかもが付け焼き刃な感じが否めないのだ。
それは、「人命に関わらない」ということでそれほど探究を必要としないということも関係しているのかもしれない。
だからこそ、逆に、知識をきちんと身につければ、エクステリア界隈ではきらり光る存在になるのではないか。
エクステリアこそ、コンクリートを極めよう。
コンクリートを制するものは、エクステリアを制する。
「生コンをもっと身近に」
生コンポータルは、エクステリアの役に立てる。
生コンポータルの使命だ。
宮本充也