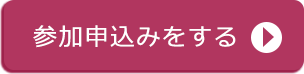2021/01/18
【静岡】「そもそもコンクリートというものは不均一に仕上がるもの」

透水性コンクリートが選ばれる理由の1つに、「色むら(コテむら)がない」「ひび割れが目立たない」と言うものがある。生コンポータルは「生コンでいいこと」をお届けするメディア。半製品生コンを日々現場で取り扱う全ての人たちに知っておいてほしいこと。「そもそもコンクリートというものは不均一に仕上がるもの」。
背伸びしないで事実を伝える
戸建て住宅外壁に発生した充填不足が原因のジャンカに近い色むら。
After写真では、表面に発生していた不均一が見事自然な風合いに加工されている。
⚫︎参考記事: 【兵庫】「色合わせって頼むとすごい高額を請求されるんだよね」
なぜか、思考停止に陥る、通常フロー以外の作業は「自分とは関係ない」という錯覚。
時代は変化している。
土間コンだってそうだ。
16年を数える透水性コンクリート普及の歴史。
「土間コン以外なら、他当たってください」
すぐに、そんなふうに答える。
自分とは関係ない。
どこか特別なこと。
その最たる理由は、「知らない」。
知らない、ということは、自分とは関係ない。
ドライテックの場合はまだましだった。
財布を握る施主が直接困る、「草むしり」「ぬかるみ」「水勾配」という悩みがある。
インターネットの時代、彼らはすぐにその悩みの解決に向けて主体的に検索することができる。
彼らはすぐに、「雑草対策」「舗装」「排水のいらない」ドライテックという存在を知る。
その知識を持って施工者に「ドライテックという舗装をお願いしたい」と要請することができる。
だから、比較的知られやすい、ということができる。
一方の、色合わせ補修。
コンクリート表面に発生してしまった不均一な仕上げ面、見た目の問題。
これは通常施主の目に触れる前に施工者がなんらかの対応を迫られる。
「施工にけちがつく」という懸念から、そして無知から、高額な請求に泣き寝入りして表面の問題を施主の目に触れる手前で解消する。
たとえその施工不良が施主の目に触れたとしても、プロの施工者が困り果てて「こんなんなっちゃいました」と説明している。
まさか、そのコンクリート表面を見事な打ち放しコンクリートに変身させてしまう技術があろうとは想像できない。
何せ、その技術は門外不出、なるべく人に知られないよう知られないよう、限定的に流通していたものに過ぎないから。
この特殊技能(色合わせ補修)は毎日開催されている生コンポータルのオンラインセミナーでも30分程度でいろはを習得できる。
ある程度長年建設に携わっていれば知っているはず。
「そもそもコンクリートというものは不均一に仕上がるもの」
半製品を現場に持ち込んでその場で造成するのだ。
工場で完全に管理下に置かれた状態で製造されるものとは違う。
不均一であって当然。
その不均一性が打ち放しコンクリートの魅力といってもいい。
「ジャンカは神様からの贈り物」なんて名言を残した建築家もいるくらいだ。
だから、プロの施工者としては、打ち放しコンクリートはどういったものかを適切に伝える義務があると思う。
勝手な期待値を持って、勝手な評価を下さないように、あらかじめ説明しておくのだ。
それが嫌なら、打ち放しコンクリートなんかやめてくれ。
塗り壁で仕上げるか、あるいは灰色のペンキで塗りたくってお好みの均一な壁にしたらいい、と。
背伸びしないで事実を伝えることが適切な認知の第一歩なのだと思う。
このところ急成長を遂げている透水性コンクリート《ドライテック》が施工者に人気なのもこの点だ。
「ひび割れが目立たない(見えない)」
「コテむら(色むら)が発生しない」
つまり、従来の土間コンの見た目の問題解決、という点が評価されている。
施主に事実を伝えた上で、さらに「見た目の問題解決」という意味では、壁・床ともに色合わせ補修は有益な「生コンでいいこと」だ。
習得していて邪魔になるものではない。
知らないだけで、炎上している建設現場。
知っているだけで、眉一つ動かさずやり抜ける人々。
縦割り・階層で閉鎖的になりがちな建設産業にあって、「水の次に流通する材料」生コンクリートのメディア・生コンポータルの使命は、「知らない」を「知っている」に変えること。
その0 or 1は大きな差を建設現場に届けることになる。
「そもそもコンクリートというものは不均一に仕上がるもの」
宮本充也