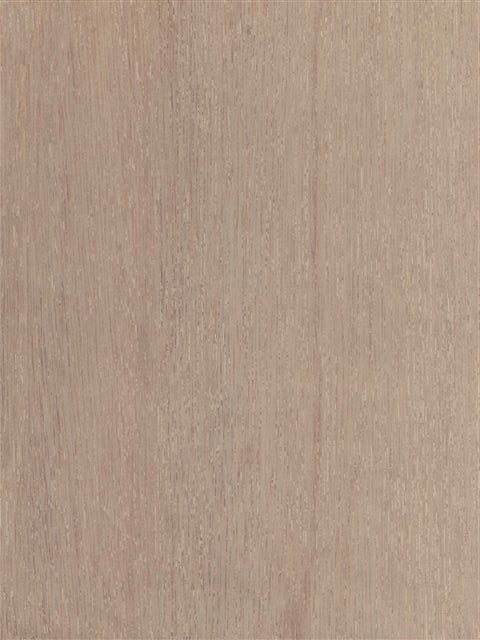2016/08/07
「むき出しのコンクリート色々」出口論より入り口論

夏だ。
毎年言っていることだけど、
今年の暑さは異常だ。
体に障る暑さと言わざるを得ない。
12時~15時くらいの間の日差しには悪意を感じざるを得ない。
夏だ。
川辺でバーベキューだ。
木陰でのんびり涼みながら一日をすごす。
そうしているときっと生コンのことを思い出してしまうものだろう。
夏にひんやりとしたコンクリート打ちっぱなしに寄り添い、
ほっぺをあてると、そのコンクリートが創られたころの記憶に触れたような、
貝殻に耳を当てると波の音が聞こえるような。
どれだけロマンチックに描写しても、これは生コンブログであるため、
さて、生コンの話題に移りたいと思う。
打ちっ放しコンクリート。
何をイメージするだろうか?
(打ちっ放しコンクリートで画像検索(Google)すると上記が2番目にヒット)
きっと写真(上)のような瀟洒でモダンな建築のコンクリート表面を想起するのではないか?
ただ、打ちっ放しコンクリートには写真(下)のように、
瀟洒とは言えないものもあるが、これも実は立派なコンクリートの打ちっ放し。
なぜ、同じコンクリートを打ちっ放しにしているのに、こうまで雰囲気が違うのか?
感じたことはないだろうか?
通り雨が染めていくコンクリートの壁と、
おしゃれなコンクリート打ちっ放し住宅の壁、
同じ打ちっ放しのコンクリートなのに、なんだか雰囲気が全然ちがう。
この秘密は実は型枠と呼ばれる「生コンがおさまる箱の内面」にある。
パネコート
と呼ばれる、つるっつるに表面加工された型枠を利用して生コンを工事すると、
表面は光沢を帯びしっかりと施工されていれば黒光りした堅牢な雰囲気をまとう。
一方、打ちっ放し建築を想定していない一般の型枠、
「普通べニア」
で生コンを公示した場合、木目がそのままコンクリート表面に転写されたりして、
一般にはイケてないとなるところだが、逆にこちらを好む超マニアックな方もおられる。
その最たるものが、
浮造りという表現
こんな型枠を利用して中に生コンを入れて締め固める。
型枠を外すと、
こんな、とてつもなくしゃれおつな、まるで芸術作品か彫刻かのような表面が浮き出る。
そして、コンクリートの表面。
どれだけ表面に気合を入れて気をつかっても、数年たつと、
「え?お化け屋敷?」
みたいになる建物と、そうじゃない建物に分かれるのはなんでだろう?
主に土木構造物のコンクリート打ちっ放しには意匠性(デザイン性能・見た目)は要求されないので、
数年たつとコケやカビが生え始めて水が浸みこみなんだかなあ、という感じになっていく、
一方、しゃれおつ建築のコンクリート表面は10年くらいたっても、
あまり変わらない
ってのは見かけたことはないだろうか?
これにも秘密があって、コンクリート表面保護剤という分野のあまたある材料があり、
型枠を外してから表面に薬を塗られると、いろいろな効果を背景として、
コンクリート表面が保護される
打ちっ放しコンクリート建築ってのはそれだけで付加価値が高い。
通常建築に用いられるコンクリートは躯体材料として用いられるため、
意匠やデザインは塗り壁やタイルで見込まれる場合が一般。
そこをあえて「むき出しのコンクリート」でやる、というのは超イレギュラーだと考えるべき。
だから、打ちっ放しコンクリート建築を実際に施工する会社は、
打ちっ放しコンクリートに特化している場合が多く、
そうでない会社がひょんなことから打ちっ放しを受注したりすると結構大変。
担当が回ってきてしまった現場監督さんの心理は
「ババ抜きのババ引いた」
状態ともいえる。
それだけ、同じ建築でも打ちっ放し建築というのはとても特殊なもの。
そもそもコンクリートは天然素材。
工場の中ではなく、今日みたいな炎天下の中、工事は進む。
人はロボットじゃないから、暑けりゃ疲労もするし精度も下がる。
悪条件の中だろうが、創り上げられる表現だからこそ、ファンの心をつかむのも、
打ちっ放しコンクリート
の特別で特異性・偶然性の高い魅力の一つだと思う。
GNN僕たち生コン工場は生コンクリートのプロだし、
きっとどの打ちっ放しコンクリートを担当した現場監督さんよりも、
実際に多くの生コンクリート工事を見てきた経験があります。
どちらかといえば、僕たちのサービスは、
「補修」→「出口論」
ばかりが注目されているけれど、
施工する前にいろいろ聞いてもらえると、
僕たちはもっと嬉しい。
まだまだ伝えきれていないけれど、僕たちはたくさんのコンクリートの知識を持っています。
宮本充也