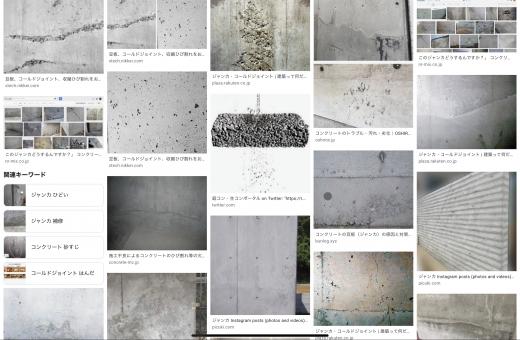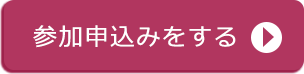2020/11/18
【静岡】「《知られたくない》vs《知られていない》のジレンマに阻まれていたすべての価値」色合わせ補修

静岡県中部地区のスポーツ施設打ち放しコンクリート庇部。打設不良に伴い施工された補修痕が目立っていたため色合わせ補修の依頼が寄せられ施工。「知られていないことは存在していないのと同じこと」。ここでも、業界のジレンマを強く感じる。
「知られたくない」vs「知られていない」
建築・土木問わず、建設現場、とにかく生コンを使う場所では必ずと言って良いほど起きる現象がある。
型枠をばらした後に露見する「打設不良」「断面欠損」という現象。
ジャンカ、豆板、ピンホール、コールドジョイント、ひび割れ。
現場を管理するすべての人たちにとって不可避な問題。
Google画像検索より引用。
こうした施工不良は機能的にももちろん、美観上も問題となる。
その上から塗り壁を施工するような場合ならまだしも、土木構造物や打ち放しコンクリート仕様のような場合には大問題だ。
「そもそも見た目は保証してません!」
なんて言い訳は通らない。
そこで、頼りになる武器。
打ち放しコンクリートに特化した特殊補修「色合わせ補修」。
特殊な道具と材料を使って周囲の打ち放しコンクリート面に調和するようにぼかす。
この技能は希望さえあればいつでも誰でもどこでも毎日でもオンラインセミナーで習得できる。
「知られたくない」「知られていない」のジレンマ。
そもそも施工不良。
ひっそり、こっそり、片付けてしまいたい。
誰にも知られず、まるでなかったかのように。
これが、現場管理者の心理だ。
一方の色合わせ補修の担い手が抱えるジレンマ。
「常に、ひっそり、誰にも知られず」
を要求されるということは、いつまで経っても「知られない」が求められる。
そもそも、「伝えない(情報発信をしない)」ことを顧客サイドから期待されているのだ。
「知られていないことは存在していないのと同じこと」
こんなに有益なスキルであっても、「伝えなければ、知られない」。
だから、その日その時、打設不良で本当に困っててこの価値・スキルを本当に必要としている人にも伝わらない。
つまり、価値は届けられない。
かてて加えて、建設産業はいかに民間とはいえ、階層構造と縦割りを前提としている。
情報の流動性はただでさえ低い。
壁と天井で区切られた構造の中を情報は回覧板方式、あるいは阿弥陀籤方式で流れる。
限定的だ。
どんなに必要とされる情報でも、一気呵成に広がるということはない。
これらが、この分野が市場として成熟しない最大の理由となっている。
インターネットと企業間連携を得て伸び代しかない建設ソリューション。
ここ数年で起きた、あまり多くの人たちに気づかれていない出来事がある。
透水性コンクリート《ドライテック》が拓いた全く新しい流通構造のことだ。
従来の縦割り階層ではない、生コン製造者と施工者、小売、そして発注者(施主)がダイレクトにつながる流通システムが創造され始めている。
ここではこれまで階層・縦割りでオープンにされてこなかったリアルな情報が無料公開されている。
施主、小売、施工者、生コン製造者、それぞれの役割の主体者はこの場所であらゆる情報を手にすることができる。
その施工者の過去の施工実績にもアクセス可能になる予定だ。
この市場は全く新しく開かれたフィールド。
言ってみれば「伸び代しか無い」。
生まれたてだからできるだけ早く走れば走ったものがもっとも栄光を手にすることができる。
守るんじゃなくて、とにかく攻めまくる。
これまでの建設産業で埋もれてきたすべての価値はこの新たに創造されたフィールドで再定義されることになる。
従来の構造で埋もれてきたすべての価値。
それこそ、色合わせ補修なんてその最たるものなのでは無いだろうか。
「知られたくない」「知られていない」のジレンマに阻まれていたすべての優位なる価値。
その価値、場所さえ変われば、もしかしたら伸び伸びと、さながらドライテックのように広がっていくのでは無いだろうか。
きっと頑張る場所(産業構造)を間違えているのだ。
ドライテックの成功(と言ってももう良いだろう)に続け。
古いけど、新しい、すべての建設ソリューションの上陸を心待ちにしている。
宮本充也