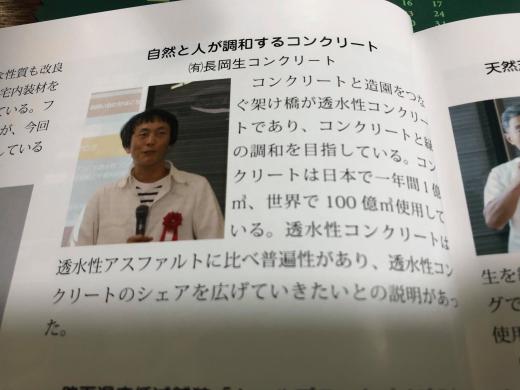2020/04/03
「自然と人が調和するコンクリートテック」一造会会長松本氏(富士植木)訪問・1級造園施工管理技士

数ある施工管理技士の中で唯一自然との調和を志向し進化を遂げてきた領域「造園」。日本の造園業界の礎を作った富士植木者の松本氏は一造会(https://www.icz.jp/)会長を6年勤められた有名人。僕を「自然と人が調和するコンクリートテック」に導いてくださった恩人。
自然を扱う造園という学問領域と業界
嘉永元年創業の富士植木は170もの歴史を持つ造園会社。
産業が興った時代に業界団体日本造園建設業協会(https://www.jalc.or.jp/index.php)を発意し、建築・土木同様に業界分野を拓いたのも同社の代表。
公共工事の一領域として市場を拓いた功績は当時イノベーションだった。
九段下にある本社には歴史を覗かせる大樹が伸び伸びと緑陰を拡げている。
営業駆け出しだった頃に頻繁に足を運んだ富士植木。
建築、土木に従事する人たちと違って、日頃草花や土と風を扱っている人たちはどこか暖かく僕は強く惹かれていった。
爾来、同社をはじめとする多くの造園関連企業に透水性コンクリートをご採用いただき、コンクリートと緑・自然というテーマで考察を深めることになる。
樹齢800年杉に新芽(https://www.nr-mix.co.jp/dry_tech/case/800_2.html)。
高じるほどに意識されるコンクリートと自然の関係性。
コンクリート、土木、建築と知識を積んできて心根に感じる違和感のようなもの。
人間が設計し作り出した工業製品は標準化を良しとする。
想定外やはみ出しものは許されない。
造園が扱う樹々や草花、そして土や風は工業製品ではない。
標準化というフレームに押し込められるものではなく、その本来の成長エネルギーを妨げず解放する仕事。
緑陰は実り、色とりどりの草花はいつしか標準化に疲れた人々の心を癒す。
僕たち人々もいつしか標準化を押し付けられていることを思い出す。
1番から100番までの序列に当てはめられ、はみ出しものは社会不適合者として可能性を奪われる。
人が自然を支配しようというここ数十年の思い上がりが生み出したコンクリート、建築、土木という学問。
それらはすべて定量化され経済性が示され効果性が解明されることが良しとされた。
人間が把握・コントロールできないものは許されないという態度だ。
一方、樹々や草花が人間の心を癒すその度合いに値札をつけることはできない。
学問としての造園は度合いや性能よりももっと抽象的な価値観を取り扱う。
松本会長のお導きで一造会の会合で発表した記事が会報誌に掲載されていた。
「合格の報告と一造会入会の相談に来たの?」
不合格だった僕に面談の最初に松本会長からの辛辣な投げかけ。
昨年「1級造園施工管理技士に合格します」(https://www.nr-mix.co.jp/dry_tech/blog/1_22.html)と宣言して臨んだ資格試験。
「自然と人が調和するコンクリートテックを標榜するなら礼儀だ」くらいのいつものテンションで自信満々に受験したが、学科試験は合格したものの記述試験でまさかの不合格。
絶対合格していると思っていた。
なのに、まさかの不合格。
施工経験に乏しいため、模範解答丸暗記丸写しが祟ったのかもしれない。
僕の勉強の仕方ははっきり言って半端ない。
ガチな猛勉強だ。
だから今回の不合格は非常にショックだった。
そしてこうも思った。
造園、自然のことを甘く見るな。
「思い上がった人間が理解(突破)できるほど甘くないことを知るがいい」
大自然からそう言われているように感じた。
今回松本さんを訪ねて一から鍛え直してもらう。
うわべだけじゃない。
心根から自然と一体となったコンクリート技術者になるために必要な経験を積むために。
一造会会長の元に弟子入りをする。
コミュニティに身を寄せ緑の活動に心身を捧げる。
思い上がった人類のコンクリート産業を軌道修正するためにも。
資格試験合格に通じる生きた知識と経験を積んで今年の12月改めて挑戦する。
絶対に合格します。
「自然と人が調和するコンクリートテック」は、コンクリートと造園という2つの学問領域の重なる場所にあるはずだ。
宮本充也