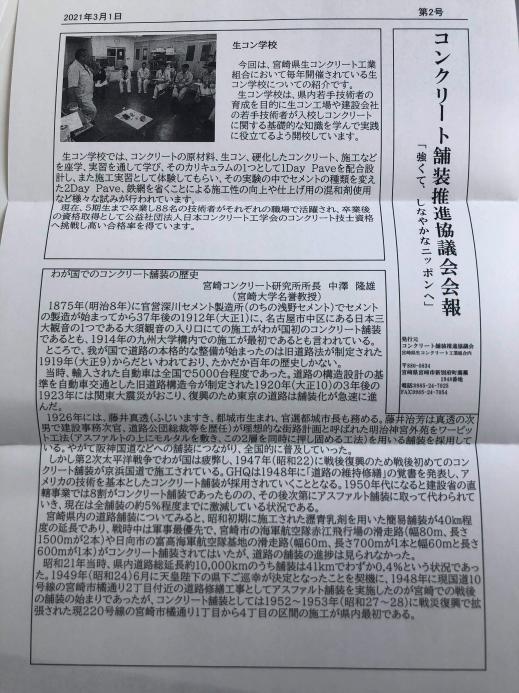2021/03/28
コンクリート舗装推進協議会会報 第2号「我が国でのコンクリート舗装の歴史」
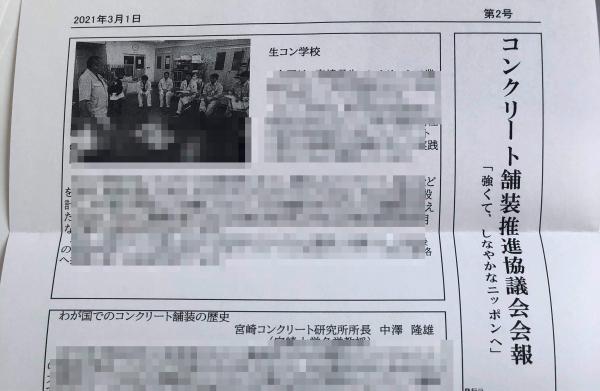
大変厳かに始まったコンクリート舗装推進協議会は工業組合ごと全生から抜けてしまった宮崎が生み出した大物木田正美が導く宮崎県生コンクリート工業組合内に組織されている。「強くて、しなやかなニッポンへ」。大物の迫力とともに届いた「我が国でのコンクリート舗装の歴史」中澤隆雄(宮崎大学名誉教授)。
強くて、しなやかなニッポンへ
⚫︎参考記事: 宮崎県生コンクリート工業組合理事長でもある木田正美氏が主催する「コンクリート舗装推進協議会」に加入しました
もう、写真だけでも、何も言われていないのに、「承知しました」と謙ってしまいそうになるほどのオーラだ。
ラオウもこれほどではなかったのではないか。
「強くて、しなやかなニッポンへ」
「はい。承知いたしました」
もう、そこには逡巡が入り込む余地はない、「はい」または「YES」しかないのだ。
そんな木田正美が号令をかけるコンクリート舗装推進協議会から届く脅迫状、もとい、会報は今回でどうやら第2号のようだ。
ここでは事務局様の逆鱗に触れない程度にその中身を一部紹介していきたいと思う。
モザイクをかけ過ぎて全く読めないと思うがご容赦ください。
生コン学校
第2号最初の特集は「生コン学校」。
宮崎県の生コンクリート工業組合には学校がある。
しかも、現在5期生まで卒業しており、その技術者88名はそれぞれの職場で大活躍をしているそうだ。
座学だけではなく、実際に生コンクリートでいろんな実験を体験できるこの学舎はきっと「強くて、しなやかなニッポン」を支える多くの技術者の拠り所となるだろう。
わが国でのコンクリート舗装の歴史
そして、これは本当に勉強になった!
知っているようで知らなかったコンクリート舗装の歴史について。
モザイクでほとんど読解不能と思うので以下に一部を引用したい。
1875年(明治8年)に官営深川セメント製造所(のちの浅野セメント)でセメントの製造が始まってから37年後の1912年(大正1)に、名古屋市中区にある日本三大観音の1つである大須観音の入り口にての施工が我が国初のコンクリート舗装であるとも、1914年の九州大学校内での施工が最初であるとも言われている。
すごい!
てことはすでに100年以上もの歴史を誇っているということなのだ。
なんとなく、「100年とかでしょ?」くらいに思っていたが、大学のそれも名誉教授が書いた文章には説得力がある。
本格的な道路整備が始まったのは、1919年旧道路法が制定されたことに端を発するという。
1923年関東大震災からの復興、第2次世界大戦以降のGHQ1948年の「道路の維持修繕」の覚書発表を皮切りに、アメリカの技術を基本としたコンクリート舗装が採用されていった。
なんと!
コンクリート舗装が我が国道路舗装の端緒だった!!
1950年代になると建設省の直轄事業では8割がコンクリート舗装であったものの、その後次第にアスファルト舗装に取って代わられていき、現在では全舗装の約5%程度までに激減している状況である。
1950年までは8割コンクリート舗装だった!
何があったんだ、この70年!!
ここから生コン産業が取り組まなければならないこと
なかなか迫力のある第2号だった。
木田正美はこの会報を通じて僕たちに何を伝えたかったのか。
「根性入れろ」
だろうか。
今気づいたが、70年前といえば日本初の生コン工場が現在のスカイツリーの建っている場所で創業を始めた頃だ。
それ以前までは8割がコンクリート舗装だった。
プラントが操業を始め大量出荷が可能になった生コンクリートなのにどうしてアスファルトに80:20から5:95まで水を開けられてしまったのか。
生コン産業は一体何やってたんだ。
だらしないじゃないか。
そして、木田正美のラブ注入。
「生コン製造者らよ、立ち上がれ」
「強くて、しなやかなニッポンへ」
県ごと全生から抜けてしまうほどの圧力の持ち主からの号令だ。
「はい。承知しました」以外の返事を知らない。
持続可能な社会において見直されるべきLCCやCO2収容性、CCUなどコンクリート舗装の可能性は大きい。
⚫︎参考記事: 「建築系、土木系に加えて、舗装系、造園系のコンクリートの専門家の時代へ」
今後研究分野としてそのフィールドは急拡大していくことだろう。
そして、木田正美が動いた。
https://www.facebook.com/192207037537451/posts/3780946528663466/
ちなみに、木田組生コンではポーラスコンクリート舗装への取り組みも熱心だ。
「コンクリートは 人の生活を 守る」
決め台詞だ。
諦めるな。
たった70年で80:20が5:95にまで変化してしまったのだ。
これ、神様とか仏様がやったのではなく、コンクリート産業とアスファルト産業の人々の営みの結果として起きた現象だ。
事実、お隣韓国では50:50で肉薄しているのだ。
今を生きるコンクリートパーソンの意識と行動さえ変革してしまいさえすれば、 5:95が10:90、あるいは30:70、生コンプラントがない時代で80:20だったのだから、本気を出せば95:5に逆転することだってできるだろう。
社会に求められるコンクリート舗装になるためには従来のように耐久性(LCC)だけを主張するのではなくサステナビリティ、SDG's、ESG評価、カーボンニュートラルといった文脈に沿う情報発信も心がけていかなければならない。
生コンポータルとしてもコンクリート舗装推進協議会の趣旨に賛同しコンクリートが世界に貢献できるよう努力していきたいと思う。
宮本充也