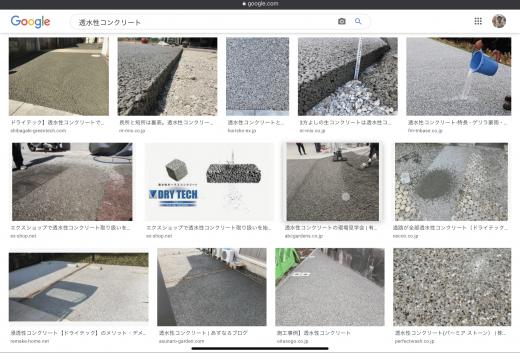2021/01/03
「透水性コンクリートの見積もりが断られてしまう本当の理由」アスファルト and/or コンクリート

「透水性コンクリート? あぁ、知ってる知ってる。ほら、高速道路なんかで雨の日も快適に走れる舗装があるでしょ?」。よく混同される、排水性アスファルトと透水性コンクリート《ドライテック》はまるで異なる、似て非なるもの。そして、機会があれば、ぜひ相見積もりを取ってみよう。「透水性コンクリートの見積もりが断られてしまう本当の理由」。
「同じ透水性の」アスファルトとコンクリートの違い
(出典:https://www.seikitokyu.co.jp/product/products/detail.php?product_id=84)
なんと、検索結果に《ドライテック》の画像が2件も表示されてしまっている汗。
Googleさんまでも混同させてしまっているらしい笑。
舗装構造は同じでも、活躍する分野が違う。
Google画像検索「透水性アスファルト」の検索結果を眺めていれば気づくだろう。
スクロールしてもしても続く公共案件の画像。
公共道路に採用されている、あるいは大規模な駐車場のように思われる画像しか見つけられない。
たまに見つかっても、「Googleさんが混同して表示させているドライテック」の写真。
《ドライテック》の主戦場とも言える戸建て住宅駐車場などのエクステリアの写真が見つからない。
同じ、「透水性」を謳っているのに、どうしてここまでの違いが、アスファルトとコンクリートとの間では起きてしまうのだろうか。
一方こちらは、Google画像検索「透水性コンクリート」の検索結果の画面。
我ながら驚いたが、その画像のほとんどがドライテックや当社がなんらかの形で接点を有している企業が発信している画像だった笑。
そして、気づくだろう。
もちろん、大型案件での採用実績はあるにせよ、そのほとんどが戸建て住宅外構工事のような小規模な現場で採用されているものばかり。
同じ「透水性」でありながら、どうしてこのような違いが生まれてしまうのか?
アスファルトの担い手は道路会社に限定される一方、コンクリートは「水の次に流通する材料」みんなの材料、という違い。
「世間に知られていない」という意味では五十歩百歩。
そう、大差ない。
でも、建設業界に限定して言わせて貰えば、アスファルトはコンクリートよりももっともっと閉鎖的ということができる。
数の上で比較してみよう。
道路用アスファルトを製造し現場に届けるアスファルトプラントの数は全国に800〜1000と言われている。
一方の生コン製造者は全国に3200以上を数える。
つまり、コンクリートは3倍以上の拠点数。
それだけ、建設事業者にとっては「身近」が(生)コンクリートということができる。
さらに、アスファルトプラントは基本的に道路会社の傘下という業態特性がある。
生コン工場のように、その辺の建材店が「売れそう」って感じで造営するものではない。
道路会社が工事を受注するために必要だから造営するのがアスファルトプラント。
そのため、アスファルトプラントの販売先は親会社あるいは関係道路会社に限定される。
一方、生コン製造者の販売先は多様だ。
そもそも独立系(と呼ばれる)の生コン製造所が大半だから、顧客は基本的に自力で開拓しなければならない。
そのため、地元に操業するあらゆる建設事業者が潜在顧客となる。
アスファルトプラントのように全然営業しなくてもいい業態ではない。
(とはいえ、生コン組合がある関係上、生コン工場もあまり営業するというわけではない)
それだけ、顧客建設事業者にとっては「身近」となる。
(大手)道路会社しか相手にしないアスファルトプラントと違って、生コン製造者は「ぽっと出」の建設事業者や個人事業主をも販売先にしている点が大きな違いだ。
普段、数千m2の案件を工事している道路会社にとって数十m2のエクステリアってどう映る?
道路業界とコンクリート業界、という区分ができる「透水性舗装」の分野。
これまで、一度たりとも住宅エクステリアの分野で透水性コンクリートと競合したことがない。
「今、透水性アスファルトで相見積もり取ってる」なんて言われたことがないのだ。
15年もやってておかしいと思ったが、冷静に考えれば上述の通り故有ることだった。
アスファルト(道路会社)、コンクリート(生コン製造所)。
いずれも、「住む海が違う」ということだった。
嘘だと思うなら、ご自宅の舗装を透水性にしたいと思った場合、アスファルトの見積もりも依頼してみよう。
そもそも断られるか、出てきたとしても信じられないほど高いものになるだろう。
普段親会社が嫌でも持ってくる案件を対応するのに忙しいアスファルトプラントにとってエクステリアみたいな小規模な現場対応など七面倒くさくてやってられない。
ここに、「透水性コンクリート《ドライテック》の見積もり依頼も断られてしまう」理由があるのかも知れない。
アスファルトとコンクリートを混同し「透水性は(道路会社から対応を)断られる」という固定観念を持った施工者が深く考えることなく施主からの希望をはねつけてしまうのだ。
「透水性は(大手)道路会社の領域」という固定観念。
もちろん、化学的に言えば、アスファルトとコンクリートは似て非なるもの。
これまでも生コンポータルではその両者の違いについて何度も紹介してきた。
⚫︎参考記事: 【京都】《インターロッキング》《アスファルト》《真砂土》徹底比較!「【祝】京都市発注《ドライテック》と仕様書に指定されました」(後編)
でも、プロダクトの良し悪しや普及の程度はプロダクトそのものの性質だけに起因しない。
どのような経緯でそのプロダクトは市場と顧客に届いているのか。
どのように、プロダクトを支えている産業・業界は発展してきたのか。
こうした、プロダクトの背景にあることの方が、実はプロダクトの性能そのものよりも重要なのかも知れない。
実際、95(アスファルト):5(コンクリート)と、大きくアスファルトに水を開けられているのは日本だけなのだから。
そして、わかることがある。
コンクリートの担い手である僕たちの意識や姿勢が変わるだけで、もしかしたら社会のあり方も変わるのではないか、という当たり前の着想。
今はまだ、「透水性といえばアスファルト」が常識。
「透水性といえばコンクリートが常識」という世界。
その世界の実現は、僕たち担い手にかかっている。
透水性コンクリートは小さい現場にか使えないのだろうか?
そんなことはない。
逆に、アスファルトは大きな現場にしか使えないのであって、コンクリートは小さくとも大きくとも、どんな現場でも適応が可能だということはすでに実証済み。
あとは、僕たちコンクリートに携わる人々に意識さえ変化すれば、世界の景色は変わるはずだ。
「透水性コンクリートの見積もりが断られてしまう本当の理由」
同じような「透水性」のプロダクトを比較していて気づいたこと。
何よりも大切なのはプロダクトそのものではなく、作り出している僕たちの意識だった。
宮本充也