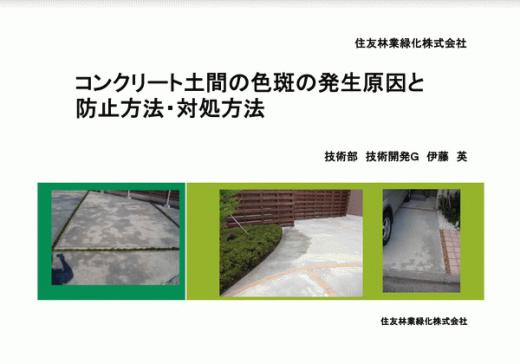2020/09/05
「【色むら】は起きないの?【色違い】とは何が《違う》の?」

よくある質問「色むらは起きないの?色違いとは何が違うの?」。透水性コンクリートはその名の通り「コンクリート」。コンクリートは「人工石」。石は樹脂製品(ポリバケツなどプラスチック製品)と違って変性しないけど、「水に濡れると色が変わる」。色むらと色違いの《違い》について。
土間コン3大クレーム《色むら》の発生要因と《色違い》との違いとは?
⚫︎参考記事: 「コンクリート土間の色斑の発生原因と防止方法・対処方法」【土間コン博士】こと住林緑化伊藤氏の講話
土間コン永遠の課題「色むら」
「土間コン」「色むら」でググったら当サイトの記事がトップに上がっていた。
懐かしい。
今も大変お世話になっている住友林業緑化の伊藤部長。
この方は人呼んで「土間コン博士」。
おそらく人類で最も土間コンクリートのことを考えている1人なのではないだろうか。
そして、そんな博士に寄せられる現場からの困った。
「土間コンの色むらなんとかならないの?」
そう。
エクステリアや建設に携わる人たちならみんな知っている。
「色むらは気まぐれにやってくる」
ということを。
(出典:https://sp.okwave.jp/qa/q9342655.html)。
施主も、施工者も悪くない。
奴は気まぐれにやってくる。
台風と一緒だ。
あなたが質素で清廉な生活を営んでいようともいまいとも、奴はあなたを飲み込んでしまう。
土間コン博士曰く「対策は無理」が土間コンの色むらの発生要因。
いろいろありすぎて、対策の施しようがないというのが結論だ。
だから、こちらを万が一呼んでくださっている土間コンの色むらが発生してイライラしているお施主さんには「運が悪かったですね」としか言いようがないのだ笑。
そして、その色むら。
主たる要因として「金鏝で仕上げる工程で発生する」ということはわかっている。
コテを当てた箇所のムラ(水分の蒸発散のムラ)がいずれの場合も原因となっているようなのだ。
つまり、金鏝を使う以上土間コンクリートは永遠にこの「色むら」という現象から逃げることができないということがわかる。
一方の透水性コンクリートの「仕上げ」は金鏝を用いない。
プレートコンパクタと言って、転圧する機械で締め固めるだけで終了。
ペーストがなく金鏝によるムラもないため、土間コンクリートに発生する「色むら」は発生しようがない。
色違いは発生します!だってコンクリートだもん
こちら、手前側が新しく施工されたドライテックで左手は以前施工されたもの。
色の違いがわかる。
同じスパン(手前側の新しい土間コン)においても、右手奥と手前側に色の違いがあるのがわかるだろう。
詭弁を弄しているのではない。
言葉遊びでもない。
色違いはコンクリートである以上「絶対に」発生すると断言しておこう。
そして、色違いが発生しなければならないとも加えておこう。
ドライテックに打ち水をしている様子。
水に濡れたところが変色(色が変わる)しているのがわかる。
乾いた箇所は白く、濡れているところは色が濃いまま。
石は水に濡れると同様に色が濃くなる。
一方、アスファルトやバケツは水に濡らして色が濃くなったりするだろうか。
かなり乱暴に言えばこれが、無機質と有機質の違いとなる。
コンクリートも石も濡れると色が濃くなる。
つまり、微細な空隙(細孔空隙)の中に水が侵入することによって色が変質するのだ。
それは施工中材料に含まれている水分の蒸発の仕方でもコンクリートの色が「乾きやすい箇所」と「いつまでも日陰」とは異なることを意味する。
「色違い」は不可避。
それはコンクリート(人工石)である以上そういうもんなのだ。
これが嫌ならアスファルトかプラスチックで駐車場を舗装すればいい。
すぐにダメになるからやめといたほうがいいけど。
石の仲間である以上コンクリートが濡れて(あるいは水分の蒸発のタイミングが影響して)色違いが発生することはあらかじめしっかりと説明しておくべき。
ただし、安心して欲しい。
施工直後はその色違いも目立つが、結局はコンクリートの内側に含まれている水分もやがては抜けていく。
徐々に色違いの度合いは緩和される。
そのうち気にならなくなる。
「色むらは起きないの?色違いとは何が違うの?」
ドライテックには「色違い」は発生する。
だって、コンクリート(人工石)だからだ。
宮本充也