2021/05/10
「吉高まり氏とコンクリート業界のカーボンニュートラル化を見る」RRCS座談会 Vol.7
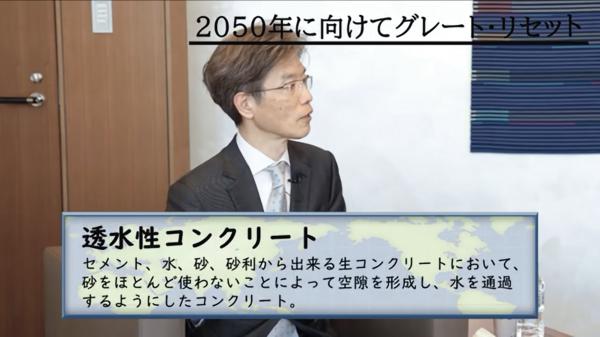
コンクリートのカーボンニュートラル化への金融界からの提言。野口先生もご自身のことを「素人」と言って謙虚に受け応える金融の分野は、僕たち生コンラストマイルからしたら馴染みのない世界。生コン、そして、金融。実は密接な関係があった。「吉高まり氏とコンクリート業界のカーボンニュートラル化を見る」
生コンと金融
環境金融の現在と未来 | RRCS対談座談会 Vol.7 吉高まり氏とコンクリート業界のカーボンニュートラル化を見る
今回で7回目となったRRCS対談・座談会。三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 経営企画部門 副部長 プリンシパル・サステイナビリティ・ストラテジストの吉高まり氏をゲストに、カーボンニュートラル、ESG、グリーンボンドと、今後の世界で必須となる‟グリーン事業"の本質とその関わり方を考える。
00:00 オープニング
01:45 環境金融の現在
04:05 ESGの本質
12:46 経済合理性の視点
18:00 コンクリート業界における課題
25:05 2050年に向けてグレートリセット
一般社団法人生コン・残コンソリューション技術研究会
https://rrcs-association.or.jp/
ご入会お待ちしております!
CSRとESGとの違い(ESGの本質)
新しい横文字に対して人々は基本冷めている。
仕方ない。
これまでも、いろんな横文字が話題となった。
で、それらはいつしか「あ〜あったね」ってあの人は今ポジションに堕するからだ。
ビジネスやってますぜ的な人がぺちゃくちゃ横文字を弄するからいつしか人々は横文字、たとえばSDG'sやらCSR、ESGやらを全てごった煮、一緒くたにしてしまう。
だが、ESGは違う。
「当社らとしてはかくかくしかじかの環境対策を実施しています」
これは、単なるCSRだという。
ESGとは、それらは当然のこととして踏まえて、「環境に関わる将来のチャンス(今はリスク)に対してどのような活動をしていますか?」を問うもの。
環境金融のトップランナーを走り続けてきた彼女が語るESG。
確かに、凄みがある。
経済合理性の視点
そして、研究者(アカデミア)のジレンマ。
「で、コストは?」
と聞かれて、モゴモゴしていると、「ああ、高いんじゃん。じゃあ、従来技術でいいよね」というリアクションに晒される。
これは、アカデミアだけではなくラストワンマイルにとっても同様のジレンマなのではないか。
いいものを作りたい。
より社会、環境に貢献できるプロダクト、テックを生み出して浸透させたい。
そんな思いを挫くのは常に、「経済合理性」という名の短期的利益の追求。
一方、ESGがフォーカスしているのは「今の利益」ではなく、「どのような理想的な将来」に対して、「今どのような活動をしているか」。
そこをきちんと組み立てることができ、組み立てるだけではなくそれを発信することができれば、投資家から資金が流入してきて、然るべき将来に向けた活動が本格化する。
それが、ESG評価以降の経済合理性の重要な視点となる。
コンクリート業界における課題
「自分たちでは何もできない」と最初から思っちゃうという負け組根性が気になる。
ユーザーから言われたことをただ後追いしようとする雰囲気がある。
それもそのはず、常にメニューはゼネコンやJISが規定する。
ものづくりの担い手、というよりも、練り屋、下請け、使いっ走り、という方が生コンの現実を表現している。
と言うのも、「(努力しようともしないでも)値段はみんな一緒」(協同組合)という現実が横たわる。
そんな低迷した状況を、グリーン・ボンド、ESG投資をきっかけに変革できる。
「みんな同じメニュー」が原則。
協同組合は常に「みなさん一緒に行きましょう」が原則。
一方、技術開発(イノベーション)においては「トップランナーが必要」なのに、現行の業界構造ではそのようなタレントを育むことができない。
これが、生コン業界に潜んでいる大きな闇。
そして、払拭(打破)すべき課題。
「(カーボンニュートラルの時代に)じゃあ、コンクリートはいらないです」って言われちゃったらどうなるんですか?
長い歴史を持ち、環境に対する悪影響が指摘されている産業であるからこそ、伸び代がある。
そう考えることはできないだろうか。
改善する。
そのことで、かくかくしかじかの貢献を生むことができる。
これを発信する。
生コン業界にとって当たり前の環境課題は投資家にとっては当たり前ではないという情報格差。
ESG、カーボンニュートラル、という風潮は単なる流行ではなく、これからの世界の全てを規定するパラダイム。
その中で、ものづくりもパラダイムシフトを起こす。
「自分たちでは何もできない」
それはこれまでの世界では果たしてそうだったかもしれない。
これからの世界では、何が起きるのか誰もわからない。
今こそ建設、生コン産業に巣食う負け組根性を払拭し、立ち上がる時なのだというメッセージを受け止めた。
2050年に向けてグレート・リセット
コンクリート舗装、道路、という分野。
「既存産業との軋轢はどうすんの?」
この問いは、上述「で、コスト(短期的経済合理性)は?」に通じる、「やら(れ)ない理由」を誘引する悪魔の言葉だ。
確かに、今の世界では道路という分野にセメント・コンクリートを適応するという活動は既存産業との二項対立という観点で語られがちだ。
しつこいようだが、ESG、そしてカーボンニュートラルの世界でこれまでの常識は全く通用しない。
「これまでがこうだったから」
ではない。
「然るべき未来はどうなのか」
に対してフォーカスし、それに対して今僕たちは何ができるのか。
野口先生から、ポーラスコンクリート舗装の可能性について言及があった。
気候変動(ヒートアイランド)に対する性能だけではなく、水を通すということはつまり空気をも通すこと。
⚫︎参考記事: 《コラム》「透水性コンクリートの本当の価値は水を透すことではないのかも知れない」
さらには、コンクリートはもとより中性化(Carbon Capture)効果が見込めるということ。
その性能をしっかりと立証し、これまでのように内向きではなくきちんと外向きに発信する。
これまでの縦割り・階層で統制・制御されてきた世界では、僕たちラストワンマイルだけではなく、トップアカデミアでさえ、既成の考え方に縛られてきた。
「何やったって、どうせダメ」
大企業に勤める人々を含めて多くの人たちの負け組根性をこれまでも僕は何度も見てきた。
吉高まりさんが興奮して語る未来への道程に僕も興奮を抑えきれない。
これまでとは違った新しいスタート地点に僕たちは今着こうとしている。
これから、全く新しいルールで「ヨ〜イドン!」が始まろうとしている。
いよいよ僕たちの時代がやってきたのだ。
普段馴染みのない金融と生コンを結びつけることで、こんなにも明るい可能性が広がるとは想像し得なかった。
僕たちラストマイルがやっていることは正しい。
インターネットと企業関連系を、これからESGとカーボンニュートラルが強く鼓舞してくれる。
追い風、伸び代しかない。
今動かないやつはもう心の底から馬鹿だと思う。
もう、マジで、気の毒だ。
僕は動く。
誰に頼まれなくとも、動く。
というよりも、動かないではいられない。
理想的な世界を作り出せるのは誰でもない僕たちラストマイルだ。
宮本充也










