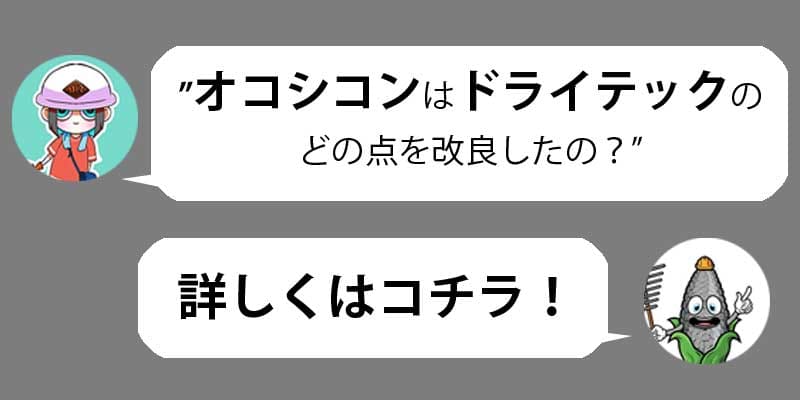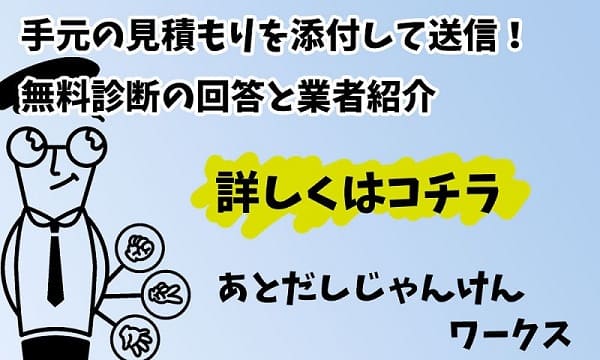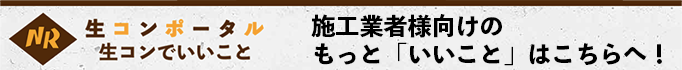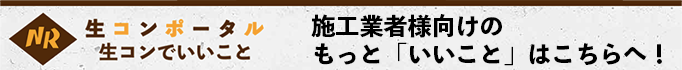透水性コンクリート オコシコンのDIY施工マニュアル【透水宣言】
更新日:2023年 12月 13日

今回はオコシコンのDIY施工方法を解説していきます。
オコシコンのDIY施工に興味がある方は、ぜひ参考にしてみてください。
ちなみに、新たに透水性を持つコンクリート「オワコン」も現在はリリースしております。
オワコンはオコシコンよりもDIYが簡単に行え、同じ透水性かつオコシコンが抱えていた剥離飛散問題も解決しています。
透水性コンクリート オコシコンのDIY施工方法
まずは、オコシコンDIY施工の全体工程を紹介します。
・生コン工場へオコシコンを発注
↓ (2週間前までに)
・施工箇所の下地作り
↓ 鋤取り→路盤工→型枠工
・舗装施工
敷設→均し→転圧
上記の手順でオコシコンを施工することができますが、どこの生コン工場へオコシコンを発注すればいいのかわからない方も多いかもしれません。
オコシコンの発注は下記マップより、お近くの施工業者を探して直接ご相談注文いただけます。
お近くの施工業者を探して依頼をしましょう。
⇒オコシコン・オワコンの材料をお求めの場合はこちらの施工業者マップから
道具の準備
オコシコンDIY施工の全体工程を確認したら、次は施工に必要な道具の準備です。
スコップ、つるはし、蓑(みの)、水糸、養生テープ、型枠材、杭、石頭ハンマー、金槌と釘、プレート(転圧機30㎏)、トンボとコテ、タンパ、ベニヤ板(4ミリ程度)、検査用プラスチック容器、土嚢袋
転圧機など購入が難しく、1度しか使わないと想定されるものはレンタルを活用しましょう。
施工工程の確認と施工に必要な道具を準備し、成功日程を決めたらオコシコンを発注しDIYに挑みましょう。
施工箇所の下地作り
ではここからが、実際の施工手順となります。
まず、オコシコンを施工する箇所で仕上げ高さの位置と位置の基準点が分かるように水糸で線を引きます。
・鋤取り→路盤工→型枠工
オコシコンを施工するためには、コンクリート材100mm、下地材100mm、合わせて200mmの高さを確保しなければなりません。
そこで鋤取りを行い、施工箇所を掘り下げて平らに削り取ります。
鋤取りで残土が発生した場合には、残土置き場をあらかじめ確保しておき、処理してほしい量を土嚢などに詰めておきましょう。
・鋤取り→路盤工→型枠工
鋤取りを行った箇所に、路盤材を流し込みトンボで平らに均し、転圧機をかけます。
・鋤取り→路盤工→型枠工
路盤工の施工が完了したら、オコシコンを流し込むための型枠工を施工していきます。
ホームセンターで手に入る木材で、高さは必ず10㎝以上の物を選びましょう。
型枠の上端を最初に決めた水糸の高さに合わせます。
型枠が自立して立つように、釘などを使い固定します。
施工箇所を型枠で囲めたら、施工箇所の下地作りの工程は完了となります。
オコシコンが届く前に、下地に水を撒き濡らしておくようにしましょう。
オコシコン施工中に下地が乾ていると、オコシコンが乾いてしまうのを防ぐためです。
舗装施工(オコシコン)
施工箇所の下地作りが完了し、水を撒いて濡らしおき、ミキサー車でオコシコンが届いたら品質検査を行います。
オコシコンをプラスチック容器に移し、30回程度しっかりと上下に振ります。
蓋を空け、ペーストが多すぎて目詰まりしていないか、全体的に艶があり濡れた状態になっているのかを確認します。
オコシコンを出し、容器にペーストがほとんど付着をしていなかったり、逆にべったりと付きすぎている場合、生コン屋さんに材料の調整をお願いしましょう。
・敷設→均し→転圧
品質に問題が無ければ、オコシコンを敷設していきます。
(オコシコンの施工に、ワイヤーメッシュは必要ありません。)
・敷設→均し→転圧
トンボなどを使い広げていきますが、少し高めに敷設して均すようにしましょう。
100mmの厚さで施工をする場合、転圧によって圧縮されることで沈むため+20mmほど高さに余裕を持たせます。
こちらはタンパと呼ばれる道具で、転圧機では仕上げにくい端の部分を仕上げることができます。
タンパを掛け終わったら、転圧の準備を行います。
ベニヤ板を敷いて転圧機をかけることで、均一に転圧を行うことができます。
その際、ベニヤ板を事前に濡らしておくことで、オコシコンの渇きを防ぎつつベニヤ板への付着を防ぐことができます。
・敷設→均し→転圧
均一に全体を転圧することでオコシコンのDIY施工は完了となります。
透水性コンクリートオコシコンは施工後すぐに、人が乗っても大丈夫なコンクリートです。
しかし、車など重たい物を乗せる時には、オコシコンがコンクリートであるがゆえに必要な期間として1週間〜2週間の期間をあけましょう。
型枠も施工後すぐに外さず、1週間前後様子を見て外すようにします。
もっと簡単に透水性コンクリートでDIYするなら「オワコン」

オコシコンのDIY施工方法を解説してきましたが、新たな透水性コンクリートとして「オワコン」が登場しました。
オワコンはオコシコン同様に透水性を持つコンクリートで、水たまりやぬかるみなどの水はけ問題、雑草などの対策ができます。
特に施工方法がオコシコンよりも簡単で「撒いて→均して→締め固める」だけで施工できるのです。
オコシコンだと乾きが非常に早く、現場へ到着してからすぐさま施工をスタートする必要がありました。
オワコンは保水性が高く、ゆっくり施工を行ったとしても乾く心配が無く、DIY初心者の方が施工手順を確認しながら施工しても全く問題ありません。
(オワコンの場合は施工の手順を確認しなおさなくても、撒いて→均して→締め固めるだけで施工できます。)
さらに注目してもらいたいのが、コンクリートとしての材料価格です。
| 材料 | 工事を依頼 | DIY | 透水性能 | DIY難易度 |
|---|---|---|---|---|
 砂利+防水シート |
10万円 | 4万円 | 〇 | ★ |
 土間コン |
15万円 | 5万円 | × | ★★★★★ |
 オコシコン |
20万円 | 13万円 | ◎ | ★★★ |
 オワコン |
9.7万円 | 4万円 | ◎ | ★★ |
金額はすべて税別です。
※「工事を依頼した場合」の金額に、以下の作業は含まれません。
・障害物撤去
・掘削・残土処分・下地工など事前工
オワコンは安価でお手軽舗装材の砂利+防水シートと近い価格で購入することができるのです。
同じ性能、施工は初心者にもやさしく、価格も安い、つまりオワコンの方がコストパフォーマンスが圧倒的に高いコンクリートとなります。
少し施工で凹凸が生まれてしまったりした場合の補修も、簡単に行うことができるのでおすすめです。
オワコンもオコシコン同様に施工業者マップより、お近くの施工業者を探して直接ご相談入手いただけます。
家周りの水はけ雑草対策をDIYで解決するなら、ぜひオワコンの施工をご検討ください。