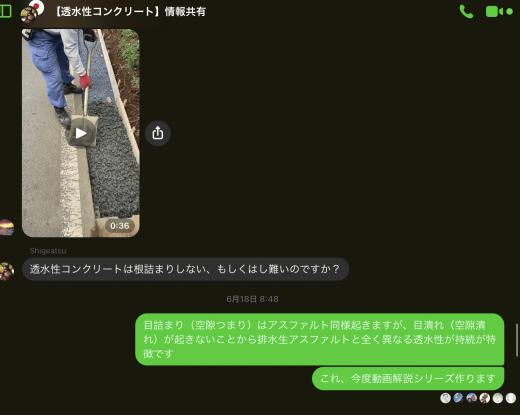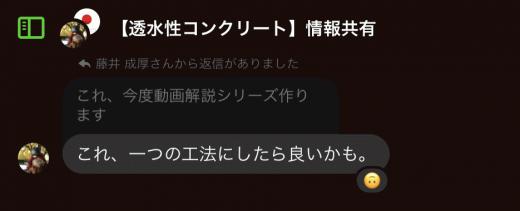2021/06/20
【千葉】「φ200の有孔管を入れそのまわりに6号砕石を入れ溝蓋部分を透水性のコンクリート」常総コンクリート・東葉興業

千葉県銚子市。役所より「道路わきの側溝が泥が詰まり流れない」「φ200の有孔管を入れそのまわりに6号砕石を入れ溝蓋部分を透水性のコンクリート」と指定。施工東葉興業、いつもアスファルト舗装施工をやっているため手慣れた様子。
製造:常総コンクリート(担当:岡根重雄)、施工:東葉興業(担当:朝比奈貴志、U字溝300×300、L=9m、φ200有孔管、6号砕石、100mm厚、4名、30分、タイムラプスあり)
施工動画
やったぜ!役所案件
「道路わきの側溝が泥が詰まり流れない」
どこにでも有るような田舎の風景。
よく見ると土に埋まった側溝(U時溝)。
役所から「φ200の有孔管を入れそのまわりに6号砕石を入れ溝蓋部分を透水性のコンクリート」という指定があった。
10年、20年前なら、この役所からの指定は受け皿を見つけることなく漂いやがて消えてしまっていただろう。
この規模に供給可能な透水性コンクリートの現実的な選択肢が当時はなかった。
現在全国620を数える生コン工場の供給インフラが確立されている。
「透水性コンクリートで」という希望はきちんと着地する。
消えてしまうことなく、形となる。
市場と顧客から寄せられたニーズには常総生コンが応える。
以前茨城県の行方コンクリートで開催されていたドライテックの製造・施工見学会に参加していたこともあり、施工東葉興業から寄せられた相談に「製造できます」という答えを返す。
⚫︎参考記事: 【茨城】「実際どのくらいの水を吸収(貯留)してるの?」「駐車場2台分でおよそ1tの水を貯留する」小沢建築・行方コンクリート
施工Before。
溝蓋を撤去された側溝の中にはφ200の有孔管が設置され、その周りを透水性の良好なビリ砂(6号砕石)で巻きたてられている。
その上層100mmをドライテックで舗装することにより排水設備とする工事だ。
それでは、施工スタート。
施工After。
U字溝300×300、L=9m、φ200有孔管、6号砕石巻きたて、上層100mm厚のドライテック。
4名で30分で完成。
同社らはもともとアスファルト舗装の作業に慣れていることもあり非常に手際の良い施工となった。
側溝の代わりとして有孔管の周りをビリ砂利で巻いた上に溝蓋のようにドライテック(透水性コンクリート)を打設している動画。これ、新しい標準的な工法になるかも?
「それでもまた水を吸い込まなくなるんじゃないの?」
透水性コンクリートの共有グループに参加しているRRCSの藤井さんからの素人質問。
「透水性コンクリートは目詰まりしない、もしくはし難いのですか?」
答えは、「アスファルトも、コンクリートも、目詰まりしない、し難いという差はない」となる。
また、チャットでの回答にも有るように、目詰まり(空隙つまり)はアスファルト同様起き流ものの、(コンクリートの場合)目潰れ(空隙潰れ)が起きないことから排水性アスファルトと全く異なる透水性の持続が特徴となっている。
この点については、別途解説動画シリーズでじっくり説明したいと思う。
空隙「詰まり」と「潰れ」は似て非なるものであって、つまりは回復可能だが、潰れは戻すことはできない。
よって、コンクリートは長年その透水性が約束される。
透水性コンクリートの目詰まりを回復させる方法の実演
⚫︎参考記事: 「どうせ目詰まりするんでしょ?」ハイウォッシャーによる驚異の回復力実演
ハイウォッシャーのような大袈裟な設備を持ち出すまでもなく、ちょっと水圧を強くしたホースの水程度でドライテックの目詰まり(空隙つまり)は回復する。
空隙はいついつまでも保持される。
これが、コンクリートの最大の強みだ。
藤井さん、僕もそう思います。
これ、一つの工法ですね。
そして、その工法は各地に隈なくドライテックを供給するインフラが整備されているからこそ。
これが、ドライテックの最大の強みだ。
特定のどこそこでしか買えません、なんてプロダクトは単なるエゴの押し付けでしかない。
世の中に貢献できる価値とは言えない。
僕たちが創り出してきたのはプロダクトではなくこの特徴的な流通インフラだと言える。
生コンラストワンマイルたちの垣根のない共感の輪と言っていい。
そんな感じで、とりあえず、今では役所からの頭でっかちな指定に対してもきちんとお応えすることができるようになった透水性コンクリート。
ロットは0.5m3とか少量から運ばれている。
これって、結構な強みだと思う。
電気、水道、生コン。
電気、水道、ドライテック。
「φ200の有孔管を入れそのまわりに6号砕石を入れ溝蓋部分を透水性のコンクリート」
仕様書に記入することはできる。
指示することも簡単だ。
ただ、その指示を具体的な形にして示すためにはそれなりのプロセスがなければならない。
僕たちはプロダクトではなく、プロセスを作っているのだと思う。
いよいよ世の中の景色をより美しく変え始めています。
宮本充也