2020/05/18
「《施主》と《施工者》の隔たりに立つ」週刊生コン 2020/05/18
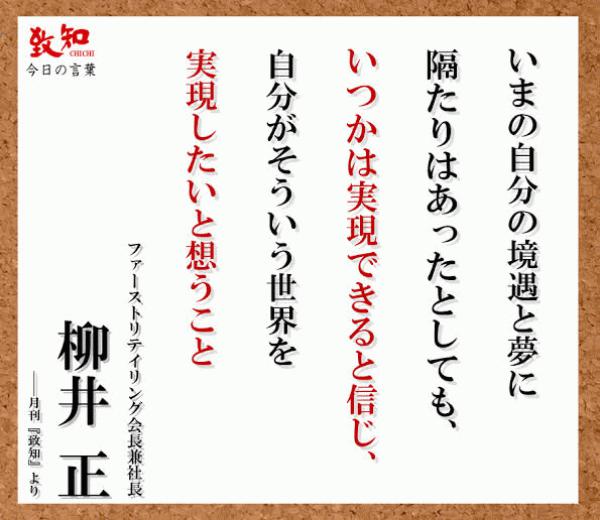
生コン産業(Bto B)にあって長年情報発信をしていると身につまされる《施主》と《施工者》(あるいは《製造者》)の間にある隔たり。そのままにしていてはいつまでも価値は市場と顧客に伝わらない。先週1週間も、「《施主》と《施工者》の隔たりに立つ」生コンポータルの活動(週刊生コン 2020/05/18)。
(トップ写真出展:https://plaza.rakuten.co.jp/miyahyon/diary/201711280011/)
「いよいよ《カインズ》でも販売カウントダウン!」ドライテック・DIY
https://www.nr-mix.co.jp/dry_tech/blog/diy_34.html
ホームセンター大手カインズでの本年6月上旬実験販売に向けて詰めの協議が行われている。
製品の価値の発信の仕方にはいろんなあり方があると思う。
「なかなか手に入らない」
「1年待ち」
「予約が1分で埋まってしまい、次の予約も来月」
希少性ももちろん価値の1つだし否定はしないけれど、
⚫︎大地に蓋をしない(自然と人が調和する)
⚫︎樹木や草花の根系や地下水系に雨水を還元する
⚫︎水たまり、水はけ、ぬかるみから解消される
⚫︎草引き(雑草)から解放される
(以上は一般・施主にとって得られる価値)
⚫︎土間コンと違って30分で施工が終わる
⚫︎水勾配(水はけ、排水)の検討が楽になる
⚫︎メッシュがないから施工前中何も楽になる
⚫︎ひび割れ、色むらの問題が生じにくい
(施工者にとってのメリット)
こうした価値はレクサスやポルシェのように特別な成功者でなければ得られない勝ちであってはならない。
透水性コンクリート普及15年の歴史を振り返れば、日本全国「街の風景」として溶け込んでいるカインズのような大手ホームセンターに透水性コンクリートの展示サンプルが設置されることにかんがいも一入だ。
これこそ、一般と産業の隔たりや溝を解消すること。
【施主】「どこで実物見れるの?」【施工者】「ぶっつけ本番怖いな」無料展示サンプル設置について
https://www.nr-mix.co.jp/dry_tech/blog/post_1131.html
そんなカインズでの透水性コンクリートサンプル展示にアイディアを得て始まるプロジェクト。
無料展示サンプルの全国設置。
⚫︎施主「とても興味はあるけれど実物見てみないことには・・」
⚫︎施工者「最近話題のようだけど、ぶっつけ本番は怖いよ・・」
そんな両者の希望を1発解消する取り組み。
生コンポータルでは無料で型枠と材料を提供し、サブロクサイズ(900×1800)の展示を見積もり依頼中の施工者のオフィスやお店の空きスペースに設置します。
この経験を通して、
⚫︎施主「ああ、こんな感じの風合いで、水もこのくらい通すのね」
⚫︎施工者「なるほど。これなら簡単に施工できるぞ」
納得していただける。
誰かの特別な製品ではなくて誰にとっても当たり前のありふれた価値にする。
ユーザーフレンドリーを構築する。
施主と施工者(製造者)の隔たりを解消することが大切なんだと思う。
「DIYでウッドデッキを作るマニュアル動画」ドライテック+ウッドデッキ
https://www.nr-mix.co.jp/dry_tech/blog/diy_35.html
DIYこそ施主にとってBtoB建設資材をもっと身近に感じてもらえるためのインターフェースとなる。
映画「透水宣言」シリーズでは「建設(生コン)をもっと身近に」感じてもらいたいという趣旨でDIYマニュアル動画をリリースしている。
ドライテックは一般の方でもDIYに挑戦する事のできる生コン。
施工者の仕事を奪うのではない。
施主に生コンをもっと身近に感じてもらう「施主と施工者の隔たりを解消する」事がそのまま施工者(や製造者)の活躍のフィールドを広げることにつながる。
「知られていないのは存在していないのと同じこと」
だから、僕たち生コンポータルは何も隠さず全てをありのままに伝える。
【長崎】「打ち放しコンクリートが好きな《施主》と嫌いな《施工者》の溝を埋める」色合わせ・杉板型枠
https://www.nr-mix.co.jp/rc/blog/post_459.html
産業(建設、生コン)が発展していくといつしか手段(業界)が目的化してしまうこともある。
建設、生コン産業の地位向上。
それは、目的ではなくて結果。
なのに、多くの産業団体はその結果を目的にして活動しているように見える。
産業の地位向上は市場と顧客に価値を届ける(喜んでもらう)こと以外に方法は無い。
だから僕たち産業人はひたすら価値を作って市場と顧客の審判に委ねなければならない。
「顧客が好きな打ち放しコンクリート」
一方でその施工は難航を極める。
よほど慎重に準備をしたとしても失敗するときは失敗する。
だから結果施工車は施主の思いに反して施工そのものを敬遠するようになる。
施主(BtoC)と施工者(BtoB)の隔たり。
生コンポータルの役割はその隔たりに立つことで問題解決策を届けること。
「生コンをもっと身近に」することが使命。
インターネットの普及でいよいよ生コンもBtoCの文脈に広がりつつある。
僕が生まれたとき(1978.08.22)にはなかったインターネット。
就職したときだってまさか生コンにグローバルやインターネットが関係するなんて思ってもみなかった。
それが、今や産業の発展のためには必要不可欠なものになりつつある。
インターネットがなければ産業のフィールドはどんどん縮小してしまう。
だから、情報発信をする。
知られていないだけで実は身近な建設や生コンは一般の人たちにとってとても役に立つ存在。
それを知ってもらうことで、社会貢献が果たされ、結果として僕たちの地位は向上すると信じている。
宮本充也










