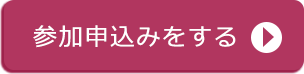2020/12/22
【長野】《墓地》「土間コンにした場合、排水はどうするの?」仲川石材・高沢生コン(前編)

長野県飯田市。施工・仲川石材はほとんどお墓の仕事だが墓地の周りのフェンス等は施工するという。以前に高沢生コン様の見学会で、「いつか使ってみよう」と思っていた。近隣から「土間コンにした場合、排水はどうする?」と指摘されたため、「透水性コンクリートで浸透させます」と採用された。(前編)。
製造:高沢生コン(担当:小林恵正)、施工:仲川石材(担当:仲川正博、前編50m2/100m2、100mm厚、4名、4時間)
排水、どうするの?
施工スタート。
施工の仲川石材は普段墓石工事を専門としているが、以前製造高沢生コンで開催された見学会に参加して以降、「いつか使ってみよう」と思っていた。
墓地整備に際して近隣住民から、「土間コンクリートで舗装した場合の排水」について指摘があった。
「透水性コンクリートなら路面で排水し、地下に雨水が浸透していく」
見学会参加での知識が役に立ち、近隣も納得した形で工事が始まった。
⚫︎参考記事:「日本の地面が変わる?!【生コンの本気】」
なお、こうした見学会は全国各地で開催されている。
ここで賢明な施工者なら気づくことがる。
生コン車から直接材料を荷下ろししている!
通常、従来の土間コンクリートであった場合ワイヤーメッシュと言って路盤の上には配筋されている。
そのため、生コン車の進入はおろか、写真のような足元が安定したスムーズな施工は望むべくもない。
一方の透水性コンクリートの施工であれば、「転圧コンクリート舗装」の一種に数えられ、配筋の設置は不要となっている。
それに、「どうせ水通しちゃうからメッシュ筋も錆びちゃうしね」である。
透水性コンクリートの特徴に挙げられるのは、「施工のしやすさ」ということがある。
作業をしている方々の足元を見れば一目瞭然。
「あれ?長靴は?」
である。
10年前の土間コンの施工現場にこんな格好で現れたら、「お前素人か」と先輩からなじられるところだ笑。
こちら仕上げ状況はおなじみ薄ベニア転圧。
プレートコンパクタ(30kgタイプ)の取り扱いに慣れていない場合、この方法がおすすめ。
北陸富山のあづまコンクリート墨田さんが開発した方法。
ベニアを挟むことでプレートの荷重は分散され、プレートマークと呼ばれる凹凸(クレームの原因)は回避される。
⚫︎参考記事:「2代目まさつぐが伝授?【透水性コンクリート】絶対に失敗しない仕上げのコツとは」
続いて、2レーン目。
こちらもドライテックの特徴。
簡単に取り外し可能な型枠で任意の幅で施工ができる。
この施工幅(施工フロント)はあまり広げない方が良い。
広げすぎるとかかる作業人員もそれだけ増大してしまう。
従来の土間コンでは、仕上げ直後に型枠を撤去するなんて芸当はとてもできない。
これも、ドライテックの強みの一つに数えられる。
前半戦50m2施工終了。
レーンごとに分けて施工。
お気づきの通り、大面積を一気に施工するのとは違って、狭い幅での作業を延々と繰り返す。
敷設された材料をトンボで平坦に均してプレート転圧。
単純作業の繰り返し。
だから、100m2だろうと、1000m2だろうと、やること一緒。
後編では、残り50m2の施工、いよいよ完成となる。
(後編に続く)
宮本充也